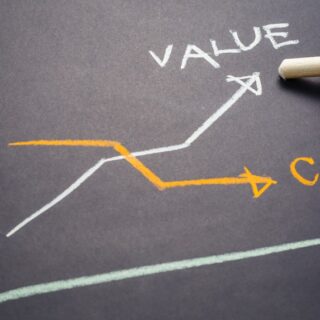企業価値の算定は、譲渡オーナー・譲受企業の両者にとってM&Aが成功するか否かの重要な要素となります。本記事では、M&Aを検討している経営者に向けて、企業価値評価が重要である理由や算定方法について分かり易く解説しますので、お役立てください。
「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」
そのような漠然とした疑問をお持ちではありませんか? みつきコンサルティングでは、本格的なご検討の前でも、情報収集を目的とした無料相談を随時お受けしています。まずはお話をお聞かせください。
のタイミング(いつ行うか).jpg)
M&Aにおける企業価値評価とは
M&Aにおけるバリュエーション(企業価値評価)とは、資産・負債の検証による時価評価、過去・現在・未来における収益性、取引先や技術力など様々な企業価値の要素を検討し、譲渡企業の株式価値を算定した結果のことを言います。
何を目的に、どの立場(譲渡側・譲受側など)から見ての企業価値なのかにより、算定結果は異なります。利益が相反する立場の譲渡側・譲受側の交渉に活用される企業価値算定となりますので、公平を保つ為、一般的には第三者機関に評価を依頼することが多いようです。
企業価値評価は、なぜ重要?
M&Aは、譲渡側と譲受がM&A取引金額にお互いが合意しなければ、成約することはありません。よって譲渡側・譲受側両者が納得できるよう、適正かつ公平なバリュエーション(企業価値算定)が重要となります。譲渡側・譲受側の両社が失敗のないM&Aとする為、しっかりとしたバリュエーション(企業価値算定)の実施をお勧めします。
譲渡側にとっての重要性
譲渡側は、できるだけ高い金額で譲渡したいという傾向にあります。実際の企業価値よりも希望譲渡価額が高いと、譲受を検討してくれる候補先を見つけることが困難になる為、注意が必要です。
M&Aを相談しているアドバイザリーにバリュエーション(企業価値算定)を依頼しその結果、譲渡における最低ラインの目安金額を決めておくとスムーズな交渉が可能です。
譲受側にとっての重要性
譲受側は、できるだけ安い金額で譲受したいという傾向にあります。一方で、自社の譲受希望金額にこだわり過ぎて相場を無視していると、競合する他の譲受候補先に譲受されてしまいM&Aが成約しないという状況に陥るリスクがあります。
また、譲受後のリスク回避の為、負債の検証を行いバリュエーション(企業価値算定)に織り込むことも重要となります。
▷関連:中小企業M&Aの相談先ランキング|銀行・税理士・仲介会社の違い
企業価値を評価するタイミング
M&Aにおいて企業価値を評価するタイミングは、幾つかあります。以下では、主に譲渡側の視点から、それぞれの段階でのバリュエーションを説明します。
1.検討初期の段階
譲渡側は、M&A仲介会社等との秘密保持契約やアドバイザリー契約を締結したら、まずは限定的な情報(直近3期分の決算書など)を基に、ラフに企業価値(事業価値)を試算してもらいます。その評価結果がある程度納得できるものであった場合には、その後のステップに進めていきます。その評価結果や算定理由が到底納得出るものではなかった場合には、譲渡の検討を中断するか、譲渡以外の手段を模索していくことになります。
▷関連:秘密保持契約書とは|M&Aでの締結時期・雛形・注意するポイント
▷関連:M&Aのアドバイザリー契約とは?仲介契約締結の流れ・種類・雛型
2.意向表明・基本合意の段階
譲受企業とのトップ面談等を経て、お話が進む場合には、譲受企業からの意向表明書の提出、または(及び)譲受企業との基本合意の締結、というイベントがあります。そして、これらの書類には譲渡価格が(場合によっては金額に幅を持たせて)記載されます。デューデリジェンス前ということもあり、記載される譲渡価格には法的拘束力を持たせないものの、いい加減な金額を記載することはマナー違反です。つまり、その後のデューデリジェンスや最終交渉を経て、合理的な理由がない限りは、譲渡側からの金額の引き上げは許されない、といった意味合いで記載される金額になります。
▷関連:M&Aの意向表明書とは|目的、記載内容、基本合意書との違い、注意点
▷関連:基本合意書とは?M&Aの意向表明・最終契約との違い、記載内容を解説
譲受企業の視点では、意向表明や基本合意は、その後のデューデリジェンスを費用と時間を掛けて進めるか否かの分水嶺となります。そのため、この段階では限定的な情報のみで実施されたバリュエーションとはいえ、譲渡側に提示する買収価格は、その後の最終交渉の過程で合理的な理由がない限りは引き下げは許されないため、いきおい慎重にならざるを得ない面があります。
譲渡側と譲受側の想定価格が大きく乖離し、歩み寄れない場合には、このタイミングで検討がストップします。
▷関連:デューデリジェンスの調査項目|種類・費用相場・注意点とは?
2.デューデリジェンス実施後の最終段階
意向表明や基本合意にて(一応は)合意された譲渡価格をベースにしつつ、その金額の妥当性を検証したり、減額すべき要因がないかの確認作業等を行う譲受企業のアクションがデューデリジェンス(買収調査)です。どの程度詳しい調査になるかはケースバイケースですが、中小企業のM&Aでは、簡素な調査にとどまることも少なくありません。
デューデリジェンスが終わると、譲受企業との最終的な条件交渉を経て、最終契約(株式譲渡契約など)の締結と譲渡実行(クロージング)を迎えます。
譲受企業の視点では、「高い買い物」となることは避けたい実質論とは別に、利害関係者に説明が付く買収価格でなければならない事情があります。取引銀行や、上場企業であれば社外役員・監査役・監査法人・一般株主です。投資委員会を設置している上場会社なら、そこでの承認も必要になります。
▷関連:最終契約書(DA)はM&Aで最重要!記載項目・注意点・雛形
▷関連:M&Aのクロージングとは?流れ・必要書類・前提条件を徹底解説
企業価値評価の方法
M&Aにおけるバリュエーション(企業価値算定)は、以下の3つの視点からのアプローチ方法に大別されます。
- 将来得られる収益(インカムアプローチ)
- 過去実績を市場の類似会社と比較(マーケットアプローチ)
- 過去に獲得した利益(コストアプローチ)
譲渡対象企業の業種や業界市況に合わせて最も適した算出方法を選択することが重要ですので、M&A検討時の参考にしてください。
インカムアプローチ
インカムアプローチとは、将来の収益や予想キャッシュフローを基に企業価値を算出する方法です。事業計画や将来の予想数値を基に算出する為、恣意性を排除することが難しいという面があります。インカムアプローチの代表的な算出方法としては、ディスカウント・キャッシュフロー法(DCF法)、配当還元法など2つの手法があります。
DCF(Discounted Cash Flow)法
DCF法の正式名称は「ディスカウント・キャッシュフロー」と呼ばれ、事業から生み出される将来のキャッシュフローから企業価値算定を行う方法です。将来の見通しが立つまで事業計画を策定し、将来キャッシュフローを算出。将来キャッシュフローを、現在の価値に換算する為、割引率を決め修正をかけます。その算出金額に遊休資産や有利子負債(金融機関借入など)の足し引きを行い、株式価値を算出する方法です。
将来のキャッシュフローは事業計画を基に算出しますので、事業計画の内容次第で株式価値が大きく変動します。
配当還元法
配当還元法とは、過去2年間の配当額を利率10%で還元し、株式価値(企業価値)を算出する方法を言います。過去の配当額から将来の配当額を予想する方法となりますので客観性が保たれにくいというデメリットがあります。
投資効率の面からの算出方法となるため、M&Aの実務で用いられることはありません。また、配当還元法は、他の企業価値算出方法に比べ低い企業価値となる傾向にある為、譲渡企業にとってはM&A取引金額の交渉で不利な算出方法になる可能性があることも注意が必要です。
▷関連:中小企業の「M&A仲介」とは?流れ・費用・メリット・選び方を解説
マーケットアプローチ
マーケットアプローチは、対象会社と類似する上場会社の経営指標と比較し価値を算出する方法です。同業種の類似上場会社の経営指標と比較して企業価値を算出します。類似上場会社との比較となるため、マーケットの状況(政策や風評被害など)に大きく左右されてしまうという面があります。マーケットアプローチの算出方法としては、市場株価法、類似会社比準法、類似取引比準法など3つの代表的な手法があります。
市場株価法(市場価額法)
市場株価法は、上場会社の企業価値を算出するときのみ用いられる算出方法です。市場株価のない非上場企業では活用することができません。マーケット(市場)の影響を排除する為、過去1~6か月の市場株価の平均額を株式価値として算出する方法です。
類似会社比較法(マルチプル法)
類似会社比較法は、別名「マルチプル」とも呼ばれ、譲渡企業と類似する上場企業(業種や商流)を複数選択し、譲渡企業と選定した類似会社の経営指標を比較する方法で、重要な経営指標に倍率をかけて株式価値を算出します。
類似上場会社の指標との比較となるのでマーケットの価額を反映していることから、客観性が高いと言えます。基準となる経営指標の選択により、株式価値が変動するため、使用する経営指標の見極めが重要となります。
類似取引比準法(取引事例法)
類似取引比準法とは、複数の譲渡対象企業と類似する対象会社のM&A取引事例に基づき、各種倍率を算定しそれと比較してM&A取引金額を算出する方法を言います。
類似した対象会社の事例が複数あること、上場企業であること、財務上の数値が公表されていることなど、類似取引比準法での算出には一定の条件を満たす必要があります。
コストアプローチ
コストアプローチは、純資産をベースに株式価値を算出する方法で、簿価純資産法・時価純資産法、時価純資産+営業権法などの算出方法があります。
中小企業のM&Aではもっともポピュラーな算出方法で、過去の業績を加味し算出する為、客観性が担保されるアプローチ方法です。将来の収益を加味しにくいという面はありますが、営業権(のれん)の加算でデメリットを補うことも可能です。
簿価純資産価額法
簿価純資産法とは、譲渡対象企業の決算書に記載される純資産額を株式価額と譲渡対象企業の発行済み株式総数で割ることで1株当たりの株式価値を算出する方法を言います。資産・負債を時価評価しない為、実態との齟齬がでること、将来獲得する収益を加味することができないことがデメリットとなります。そのため、M&Aの現場で使用されることはありません。
時価純資産価額法
時価純資産法とは「純資産=株式価額」との考えから、資産の時価(時価評価)から負債の時価を引いた時価純資産額を、譲渡企業の発行済み株式総数で割ることで1株当たりの株式価値を算出する方法を言います。
資産・負債ともに時価評価することになりますので、実態にあった企業価値算定が可能ですが、将来獲得する収益を加味することができないことがデメリットとなります。
時価純資産+営業権法
時価純資産+営業権法は、資産・負債を時価評価し算出した時価純資産額に、将来獲得する収益や数値化が難しい企業価値(技術力や取引先リスト等)を営業権(のれん)として加算し企業価値を算出する方法を言います。営業権(のれん)を加算することにより、時価純資産法よりも適正な企業価値が算出できると言えます。
再調達原価法
譲渡対象会社が保有する資産や負債を、その時点で再取得する際に必要となる費用(原価)を基にして企業価値を計算します。譲受企業のM&Aニーズの1つとして投資コストを抑えるとのニーズがある場合、対象会社と同じ会社をゼロから立ち上げる場合とM&Aで譲受する場合の費用比較をすることで、譲渡対象会社をM&Aで譲受するか否かの判断基準になります。
▷関連:企業価値評価とは?流れ・費用・算定方法・M&A実務でのポイント
中小企業M&Aに適した評価手法
中小企業のM&Aでは、コストアプローチが最も多く用いられます。理由としては、非上場会社である中小企業の市場株価が存在しないことや上場会社のように会計監査がないことから、粉飾や利益調整を行いやすく決算書の正確性が低いことが挙げられます。
また、事業計画等の業績の未来予測についても、取引先や景気に左右されやすいことや事業規模が小さいなど計画がブレやすいことから過去の実績を元に算出するコストアプローチが中小企業M&Aで多く用いられる理由です。
コストアプローチの中でも時価純資産+営業権法が、過去の実績に将来の利益や数値化できない企業価値を加算できることから最も多く活用される企業価値算定方法となります。
▷関連:事業売却の相場と金額の決まり方|価格算定方法・交渉ポイント
企業価値評価のポイント
譲渡側と譲受側は利益が相反する立場にあります。お互いの立場を主張し過ぎると交渉が上手く進みません。バリュエーション(企業価値算定)方法を理解し、お互いが歩み寄る為の根拠として活用することが重要と考えます。とは言え、自社の意向をM&A取引金額に反映させることも重要ですので、それぞれのポイントを確認してみてください。
譲渡側が知っておきたい企業価値算定のポイント
譲渡側としては、できるだけ高い企業価値評価を勝ち取りたいという意向があることは言うまでもありません。高い企業価値評価を勝ち取るポイントとしては、収益性が高い、継続的な収益が、純資産額(内部留保)が厚い、上場株等の投資有価証券・不動産など含み益がある資産を所有しているなどが挙げられます。
投資有価証券や不動産などは含み損が発生する場合もありますので慎重な検討が必要です。企業価値を高くする為に一番重要なことは、現在運営中の事業を着実に取り組み収益性向上や純資産額(内部留保)を積み上げることが重要です。M&Aで譲渡するからといって事業運営が疎かにならないよう気をつけてください。
譲受側が知っておきたい企業価値算定のポイント
譲受側としては、譲渡対象企業の企業価値がM&A投資予算内に収まることが望ましいでしょう。また簿外負債など予想しなかったリスクの洗い出しや譲受後の自社とシナジー効果の検証なども重要となります。
しかし、大幅に予算を超える案件でも検討の余地があるとの認識を持つことも必要です。M&Aは、譲受後のシナジー効果を得ることが重要となりますので、予算内に収まらなかった理由を精査し譲受後のシナジーが大きくなるようでしたら検討を続けるという選択肢も必要かと思います。
譲渡企業の純資産額の内訳で現預金が多いようでしたら、役員退職金を支給することで純資産額を下げ、M&A取引価額を下げるなどのスキーム検討も有効です。
▷関連:2025年版【M&A仲介会社一覧】上場・非上場・会計系を紹介
企業価値評価に長けたM&A仲介会社の選び方
譲渡側・譲受側両者にとってM&A取引金額は、M&Aの成否を左右する大きな要因となります。
しかし、M&A取引金額を決定する為のバリュエーション(企業価値算定)は、バリュエーション理論や会計税務理論などに精通していなければ適正なバリュエーション(企業価値算定)を行うことは難しいため、M&Aに精通した公認会計士や税理士といった専門家がいるM&A仲介会社を選ぶことをお勧めします。
▷関連:M&A仲介会社の比較|信頼できるアドバイザーを選ぶポイント
バリュエーションの時期のまとめ
M&Aの成否を判断する際、M&A取引金額がいくらだったのかということは非常に重要なポイントとなります。また、M&Aは譲渡側と譲受側の利益が相反する立場の企業が交渉を重ね進めることになりますので、企業価値算定根拠を明確にした上で、お互いが納得できるM&A取引金額の決定が必要です。
みつきコンサルティングは、会計系M&Aコンサルティング会社であることからM&Aにおけるバリュエーション理論や会計税務理論に精通した会計士・税理士が在籍し、適正な企業価値算定を実施することが可能です。M&Aをご検討の際は、ご相談ください。
著者

- 名古屋法人部長/M&A担当ディレクター
-
人材支援会社にて、海外人材の採用・紹介事業のチームを率いて新規開拓・人材開発に従事。みつきコンサルティングでは、強みを生かし人材会社・日本語学校等の案件を中心に工事業・広告・IT業など多種に渡る案件支援を行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修:みつき税理士法人
最近書いた記事
 2025年6月28日関連会社・関係会社・グループ会社の違いは?子会社・兄弟会社も解説
2025年6月28日関連会社・関係会社・グループ会社の違いは?子会社・兄弟会社も解説 2025年6月28日M&Aの意向表明書とは|基本合意書との違い・書き方・雛形サンプル
2025年6月28日M&Aの意向表明書とは|基本合意書との違い・書き方・雛形サンプル 2025年6月20日M&A会計|手法別の処理・のれん等を中小企業経営者向けに解説
2025年6月20日M&A会計|手法別の処理・のれん等を中小企業経営者向けに解説 2025年6月20日M&Aのクロージングとは?流れ・必要書類・前提条件を徹底解説
2025年6月20日M&Aのクロージングとは?流れ・必要書類・前提条件を徹底解説