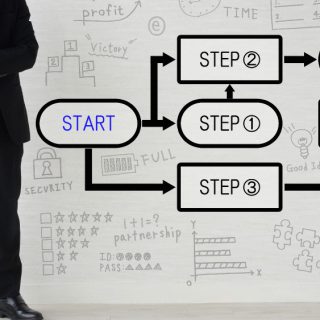M&Aは企業の成長戦略として非常に有効な手段ですが、成約までに要する期間やそのプロセスは、初めての方にとっては未知の領域かもしれません。本記事では、M&Aが完了するまでの期間と、そのスケジュールを円滑に進めるための具体的な方法について詳しく解説します。
「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」
そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。
> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ
M&Aの期間とスケジュールの全体像
M&Aは、企業の成長戦略の一つとして注目されていますが、そのクロージング(成約)までには一定の期間を要します。まるで長い旅路に出るようなもので、計画的な準備が成功の鍵を握ります。
▷関連:M&Aの流れを仲介会社が解説|中小企業の売却プロセス・進め方
M&Aにかかる期間の目安
M&Aのクロージング(成約)までの期間は、一般的に6か月から1年6か月程度かかることが多いです。案件によっては2年以上を要する長期戦になることもありますので、心に留めておくことが大切です。平均的な期間としては1年前後が目安ともいわれています。しかし、早いケースでは3か月から6か月でクロージングする事例もあり、案件毎の個別性が強いのが実情です。

中小企業のオーナー経営者が会社を売却する場合に、どの位の期間がかかるのか、以下はおよその目安とお考えください。
- 一般的な期間: 6か月から1年6か月
- 平均的な期間: 1年前後
- 急ぎ譲渡したい場合: 3か月(2か月未満の事例もある)
- 長期化した場合: 2年以上(特殊な事情がある場合など)
▷関連:M&Aにおける提携の提案書とは?作成手順・構成・企業概要書も解説
なぜスケジュール管理が重要なのか
M&Aの期間が長引くと、業界動向や相手候補先側の事情、自社の業績等が変化し、当初の目的が達成できなくなるリスクがあります。また、M&Aの情報が関係者以外に漏洩する可能性も高まります。
情報漏洩が発生すると、従業員の離職や取引先との関係悪化につながる懸念も生まれます。このようなリスクを避けるためにも、M&Aのスケジュールを適切に管理し、関係者間の円滑なコミュニケーションを保つことが非常に重要です。
▷関連:M&Aの契約書とは?NDA・仲介契約から基本合意・最終契約まで
M&Aの主要なプロセスと期間
M&Aのプロセスは、いくつもの段階を経て進められます。それぞれの段階で相応に時間を要し、まるでリレー競技のように次へとバトンが渡されていきます。
下表はあくまでも標準的なスケジュールと期間を示すものです。実際の案件では、企業規模や複雑さ、外部環境によって変動することに留意ください。
| 手続 | 期間 | 具体的な内容 |
|---|---|---|
| 事前準備・M&Aの検討 | 3か月〜数年 | M&Aの目的の明確化、事業承継の他の選択肢との比較 |
| 専門業者の選定 | 1か月 | M&A仲介会社との面談、企業価値の試算・スキーム検討、アドバイザリー契約締結 |
| 譲受候補先の選定・マッチング | 2週間〜1か月 | 譲受候補企業のリストアップ、相手企業の絞り込み |
| 譲受候補先へのアプローチ | 2週間〜1か月 | 10〜300社へ匿名打診(応相談) |
| 詳細説明 | 0〜1か月 | 5〜10社と機密保持契約締結、詳細説明 |
| 条件交渉 | 1〜3か月 | トップ面談、会社訪問、質疑応答 |
| 意向表明/基本合意 | 0〜1か月 | 1〜3社から意向表明書受領、基本合意書の締結 |
| デューデリジェンス実施 | 1〜2か月 | 財務・法務等の詳細調査 |
| 最終条件の交渉・最終契約 | 1〜2か月 | 最終条件交渉、最終契約書の締結 |
| クロージング | 0〜1か月 | 譲渡実行・対価受領 |
| PMI(経営統合) | 6か月〜数年 | 経営統合プロセス、シナジー効果実現 |
| 引継ぎ期間 | 6か月〜数年 | 経営・技術のノウハウ、社内・社外の人的関係の承継 |
これらの各プロセスで、M&Aに必要な様々な書類を作成していきます。
1 事前準備から譲受候補先の選定まで
M&Aの進行は、まずM&Aの目的を明確にすることから始まります。経営ビジョンや成長戦略と照らし合わせ、何のためにM&Aを行うのかをはっきりさせることが肝心です。事業承継を目的とする場合、他の選択肢(親族承継、従業員承継など)との比較検討も重要なプロセスです。この事前準備の段階では、M&Aの目的や戦略を明確にし、極親しい関係者(配偶者や経営幹部など)の合意形成を図ります。
その後、M&A仲介会社とアドバイザリー契約を締結し、企業価値の試算やスキーム検討を行います。この段階で、譲受候補先のソーシングや詳細な調査を行い、交渉に入るための準備を進めます。M&Aのソーシングとは、適切な譲受候補先を発掘・選定する活動のことで、M&A仲介会社の重要な業務の一つです。M&Aの調査は、譲受候補企業を選定する際の重要なプロセスです。相手先がすぐに交渉に応じてくれるとは限らず、具体的な交渉のステップに移るまでには、1か月から3か月を要することが多いです。
▷関連:M&Aのソーシングとは?実施時期・位置付け・重要性・方法・流れ
▷関連:M&Aで行われる調査|目的・プロセス毎の調査項目・成功ポイント
2 初期交渉から基本合意の締結
譲受候補先の選定が完了すると、初期的な交渉フェーズに入ります。このフェーズでは、まず匿名(ノンネーム/ティーザー)ベースでの打診から始まり、興味を示した企業との間で機密保持契約を締結します。ノンネームシート/ティーザーとは、企業名を伏せて基本的な事業概要を記載した資料で、初期アプローチに使用されます。この過程では、まずロングリストとショートリストを作成し、段階的に候補先を絞り込んでいきます。
▷関連:M&Aの「ノンネーム」とは?タイミング・記載事項・雛形・注意点
▷関連:M&Aの「ティーザー」とは?ノンネームシートとの違い・作成方法
▷関連:M&Aのロングリストとは?ショートリストとの違い・記載項目・雛形
機密保持契約締結後は、より詳細な企業概要書(IM)の開示が行われます。譲受候補先の責任者とのトップ面談や施設・工場等の見学受入を経て、譲渡オーナーと譲受候補先との間で大枠の条件が擦り合わされます。条件面で基本的な合意が得られたら、正式に意向表明書の提出を受け、内容に問題がなければ受理します。または、両者間で基本合意を締結します。この期間は、一般的に1か月から4か月程度を想定しています。複数の譲受候補先がある場合には、M&Aのオークション方式により競争入札で進めることもあります。
▷関連:企業概要書(IM)とノンネームの違い・記載内容・サンプルひな形
▷関連:M&Aのオークション方式とは?入札プロセス・相対との違い・利点
ここで双方の想いが一つになるかどうかが試される、大切な時期です。特に中小企業のM&Aでは、企業文化や経営方針の適合性が重要な判断要素となります。
3 デューデリジェンスの実施
意向表明の受理または基本合意の締結後、デューデリジェンスを受け入れます。これは譲渡企業の内部を深く掘り下げて調査する、譲受企業にとって重要な手続です。弁護士や会計士、税理士といった専門家が、譲渡企業の財務、税務、法務などを詳細に調査し、潜在的なリスクを評価します。
▷関連:M&Aの基本合意書とは?目的・最終契約書との違い・独占交渉権など
期間は譲渡企業の規模・複雑性によりますが、1か月から2か月程度かかることが一般的です。中小企業の場合、事前の準備状況が整っていれば、譲渡側が実際に応対する期間は1週間から2週間で完了することもあります。しかし、規模が大きい会社では1か月以上に及ぶことも珍しくありません。
デューデリジェンスでは、財務面だけでなく、事業面、人事面、IT面など多角的な調査が行われます。この調査結果は最終的な譲渡価格や契約条件に大きく影響するため、譲渡企業側も十分な準備が必要です。
税理士法人グループによる財務デューデリジェンス
M&Aに潜む財務リスク、見逃していませんか?
4 最終契約からクロージング
デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な条件交渉が行われます。双方にとって納得のいく合意点を見つけるまで、丁寧な対話が続きます。このフェーズでは、契約書等の作成や税務・法務対策も進められ、最終契約の締結とクロージングへと向かいます。最終契約書には、表明保証、補償条項、クロージング条件など、重要な条項が盛り込まれます。
この期間は1か月から長くても3か月程度で完了することが多いです。交渉状況や、譲受企業内の意思決定フローによって変動するため、事前に双方の承認プロセスを共有しておくことが、手続を円滑に進める上で重要です。特に上場企業が譲受企業の場合、複数の会議体での承認が必要となるため、時間に余裕を持った計画が必要です。
▷関連:M&Aのクロージングとは?流れ・必要書類・前提条件を徹底解説
5 PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)
M&Aはクロージングで終わりではありません。特に譲受企業にとっては、ここからが新たな始まりといえるでしょう。クロージング後には、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション、M&A後の経営統合プロセス)が行われます。これは、新しく結ばれた組織が、真に一体となって動き出すための大切な期間です。
PMIには6か月から1年以上、案件によっては数年かかることもあります。デューデリジェンスと並行してPMIの計画を立てておくことが成功への鍵を握ります。統合プロセスでは、システム統合、人事制度の統一、企業文化の融合など、様々な課題に取り組む必要があります。
▷関連:PMIとは|M&A後の経営統合を成功に導くポイントと失敗事例
M&Aのスケジュールが長引く要因と短縮する方策
M&Aの期間は、様々な要因によって短くなったり長くなったりします。案件進行中も、様々な環境要因により、状況は刻々と変化します。
スケジュールが長くなる主な理由
M&Aの期間が長くなる要因はいくつか考えられます。下表の要因が絡み合うことで、M&Aは予想以上に長い道のりとなる場合があります。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡企業の規模が大きい | 規模が大きくなると、関係する部門や利害関係者が増え、調整に時間を要する傾向があります。 |
| 利害関係者の同意取り付けに時間がかかる | 複数の株主の同意が必要な場合や、仕入先、取引先の事前承認が必要な場合など、外部との調整に時間を要することがあります。 |
| 譲受企業の意思決定に時間がかかる | 大企業や上場企業では、経営会議や取締役会の決議など、意思決定の手順が複雑で時間がかかることがあります。 |
| 特殊な譲受スキームを伴う | 会社分割や合併、株式交換といった組織再編行為を伴う場合、会社法上の複雑な手続が必要となり、期間が長引きます。 |
| 許認可の新規取得や契約の承継が必要 | 事業譲渡のスキームで、許認可の新規取得や既存契約の承継に地権者の同意などが求められるケースも、期間が長引く要因です。 |
| 想定外の事態の発生 | 相続問題や大規模な自然災害といった予期せぬ出来事が、M&Aのプロセスを中断させ、大幅な遅延を招くこともあります。 |
M&Aの期間を短縮するメリット
M&Aの期間を短縮することには、いくつかの大きなメリットがあります。
- まず、市場や業界の動向に左右されにくいという点があります。M&Aの期間が短ければ、その間の市場や業界の大きな変化による影響を受けにくく、当初の目的を見失うリスクを軽減できます。
- 情報漏洩リスクの軽減も重要なメリットです。M&Aは通常、ごく限られたメンバーで進められます。期間が長引くほど、従業員などにM&Aの動きが察知される可能性が高まりますが、期間を短縮することでこのリスクを減らし、従業員の離職や取引先との関係悪化を防ぐことにつながります。
- さらに、交渉疲れを防ぎ、当事者のモチベーション維持にも効果があります。長期間にわたる交渉は、関係者の集中力や熱意を削ぐ可能性があります。
M&Aの期間を短縮するための具体的な方法
M&Aの期間を短縮するためには、いくつかの有効な方法があります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 期間を明確に決める | 譲渡オーナーは、いつまでに譲渡を完了したいのか、M&A仲介会社に明確な希望を伝えましょう。期間を設定することで、各手続にかかる時間の意識が高まります。ただし、タイト過ぎる要望は十分な準備を妨げる可能性もあるため、柔軟な姿勢も大切です。現実的なスケジュールの設定が重要です。 |
| M&Aの必要書類の事前準備 | 決算書類や契約書など、M&Aで必要となる各種資料を事前に整理し、準備を進めておくことが重要です。資料が揃っていないと、企業価値の算定やデューデリジェンスに時間がかかってしまい、全体の進行が遅れる要因になります。定期的な書類整理の習慣を身につけることをお勧めします。 |
| M&A交渉時の条件の優先順位を決めておく | 譲渡オーナーは、M&A交渉において、譲歩できる部分と、できない部分を事前に考えておくことが大切です。高望みし過ぎると譲受企業が見つかりませんが、譲歩し過ぎても機会損失が生じます。どの辺りが適度なバランスか、実績経験が豊富なM&A仲介会社の担当者と、慎重に打ち合わせておくことが大事です。 |
| M&Aに関する知識を学習しておく | M&Aの検討段階から、M&Aの流れなどの基本的な知識を身につけておくことは、手続をスムーズに進める上で重要です。譲渡オーナーがM&Aに不慣れな場合、通常よりも多くの時間を要することがあります。基本的な用語や手続の理解があれば、専門家との打ち合わせもスムーズに進みます。 |
| M&Aの流れをシミュレーションする | 事前にM&Aの開始から統合完了までの手順を見通し、シミュレーションを行うことで、手続をスムーズに進めることができます。予期せぬトラブルにも臨機応変に対応でき、方向性を見失うリスクを減らせます。複数のシナリオを想定しておくことで、状況に応じた柔軟な対応が可能になります。 |
| PMI(譲受後の統合作業)の効率化・対策案を検討する | M&Aの期間短縮には、譲受後の統合作業を効率化し、対策案を事前に考えておくことも含まれます。例えば、経理や人事などのハード面での統合には人員増強を、企業文化などのソフト面での統合には経営者自身が率先して動き、M&A手続中に複数の対策案を検討しておくことが有効です。 |
スケジュール管理と円滑なM&Aのポイント
M&Aの成功は、適切なスケジュール管理と関係者間の円滑な連携にかかっています。特に中小企業のM&Aでは、限られたリソースの中で効率的に進める必要があります。
譲渡オーナーと譲受企業間のスケジュール調整
交渉期間が長引いてしまうことは、M&Aではよくあることです。そのような場合には、まず交渉の進捗状況を冷静に確認し、必要に応じて課題を見直すことが肝要です。M&A仲介会社の働きかけで、新たな視点や解決策が見つかることもあります。経験豊富な専門家のアドバイスを積極的に活用しましょう。
また、事前に譲歩できる点と譲れない点を明確にしておくことも非常に有効です。相手にとって譲れない条件が、自社にとっては譲歩できる条件であることも多いため、事前に明確にしておくことで、不必要な議論を減らせます。交渉決裂のリスクを低減するためにも、代替案の準備や条件の見直しについて、柔軟な姿勢を保つことが大切です。
交渉が長引いた場合の対応策
交渉期間が長引いてしまうことは、M&Aではよくあることです。そのような場合には、まず交渉の進捗状況を冷静に確認し、必要に応じて課題を見直すことが肝要です。M&A仲介会社の働きかけで、新たな視点や解決策が見つかることもあります。
また、事前に譲歩できる点と譲れない点を明確にしておくことも非常に有効です。相手にとって譲れない条件が、自社にとっては譲歩できる条件であることも多いため、事前に明確にしておくことで、不必要な議論を減らし、交渉決裂のリスクを低減することができます。
想定外の事態への柔軟な対応
M&Aのプロセスでは、時に予期せぬ事態が発生し、スケジュール変更を余儀なくされることもあります。このような場合、速やかに関係者と情報を共有し、必要な調整を行うことが重要です。タスクの遅れや問題が発生した際にも迅速に対応し、プロジェクトの遅延を最小限に抑えるための行動が求められます。まるで、急な雨に降られても、すぐに傘を広げるような素早い対応が、M&Aの成功には不可欠といえるでしょう。
リスクマネジメントの観点から、事前に想定されるリスクとその対応策を整理しておくことも重要です。特に、許認可の問題や主要取引先の反応など、事業継続に影響する要素については、十分な検討が必要です。
専門家との連携強化
M&Aの成功には、適切な専門家との連携が欠かせません。M&A仲介会社、税理士、弁護士、会計士など、各分野の専門家と密接に連携し、情報共有を図ることが重要です。
専門家との定期的なミーティングを設定し、進捗状況や課題について共有することで、問題の早期発見と解決が可能になります。また、各専門家の役割分担を明確にし、効率的な連携体制を構築することも大切です。
M&Aにかかる期間・スケジュールのまとめ
M&Aは、クロージングまでに半年から1年半程度の期間を要することが多く、事前準備や目的の明確化、日ごろの書類整理を行うことで、情報漏洩のリスク低減などを図りながら期間を短縮することが可能です。
当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。
完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >
著者

- 事業法人第一部長/M&A担当ディレクター
-
みずほ銀行にて大手企業から中小企業まで様々なファイナンスを支援。みつきコンサルティングでは、各種メーカーやアパレル企業等の事業計画立案・実行支援に従事。現在は、IT・テクノロジー・人材業界を中心に経営課題を解決。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修:みつき税理士法人
最近書いた記事
 2026年1月12日M&Aの手順と流れ|検討・相談~成約までを売り手・買い手別に解説
2026年1月12日M&Aの手順と流れ|検討・相談~成約までを売り手・買い手別に解説 2025年12月6日経営承継円滑化法とは?事業承継税制の認定要件等をわかりやすく解説
2025年12月6日経営承継円滑化法とは?事業承継税制の認定要件等をわかりやすく解説 2025年11月29日従業員持株会と事業承継・M&Aによる株式譲渡|仕組み・設立も解説
2025年11月29日従業員持株会と事業承継・M&Aによる株式譲渡|仕組み・設立も解説 2025年11月29日EBOとは従業員による事業承継!MBOやLBOとの違い・手順を解説
2025年11月29日EBOとは従業員による事業承継!MBOやLBOとの違い・手順を解説