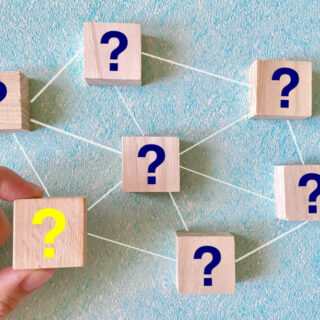事業承継における遺留分とは、後継者以外の相続人が最低限相続できる財産のことです。これが後継者への株式集中を妨げ、経営の不安定化を招くことがあります。本記事では、遺留分の基本的な知識から、生前贈与や遺言、民法の特例などを活用した具体的な対策まで、事業承継と遺留分の関係性をわかりやすく解説します。
「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」
そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。
> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ
事業承継と遺留分の関係性
会社の未来を後継者に託す事業承継は、経営者にとって一大決心です。しかし、その道のりには「遺留分」という、見過ごすことのできない大きな課題が潜んでいます。円滑な事業承継の実現には、この遺留分への対策が不可欠と言っても過言ではありません。なぜなら、対策を怠ると、後継者への経営権の集中が阻まれ、会社の経営が不安定になる可能性があるからです。
▷関連:事業承継とは|3つの承継先・対象・方法や成功事例・進め方も解説
遺留分とは?基本的な知識を解説
それでは、事業承継の鍵を握る「遺留分」とは一体何なのでしょうか。まずはその基本的な知識から押さえていきましょう。
遺留分の概要
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)に法律で保障された、最低限の遺産取得分のことを指します。たとえ経営者が遺言書で「全財産を後継者である長男に相続させる」と記したとしても、他の相続人はこの遺留分を主張する権利を持っています。この権利は非常に強力で、遺言書の内容よりも優先されるのが実情です。
事業承継においてこの遺留分が問題となりやすいのは、会社の株式が遺留分の対象に含まれるためです。後継者以外の相続人が遺留分を主張し、株式の分配を求めると、後継者が持つべき株式が分散してしまい、経営権が不安定になるリスクが生じます。
▷関連:親族内での事業承継|手順・方法・メリットとデメリット・株式譲渡
遺留分割合の計算方法
遺留分がどれくらいの割合になるのかは、法律で定められています。ここでは、その計算方法の基礎となる考え方を解説します。
遺留分の算定基礎となる財産
遺留分を計算する際の元となる財産は、単純に亡くなった時点(相続開始時)の財産だけではありません。具体的には、相続開始時のプラスの財産(預貯金、不動産、自社株式など)から、借入金などのマイナスの財産(債務)を差し引いた額が基本です。
さらに、過去の一定の贈与もこの基礎財産に加えられます。相続人に対する特別な贈与や、相続開始前1年以内に行われた第三者への贈与などがこれにあたります。
総体的遺留分と個別的遺留分
遺留分の割合には「総体的遺留分」と「個別的遺留分」の2つの考え方があります。
総体的遺留分
遺産全体に対する遺留分の割合です。相続人が直系尊属(親や祖父母)のみの場合は遺産全体の3分の1、それ以外の場合(配偶者や子など)は2分の1と定められています。
個別的遺留分
各相続人が具体的に取得できる遺留分の割合です。これは「総体的遺留分 × 各相続人の法定相続分」という式で計算されます。
| 相続人の組み合せ | 遺留分 | 各人の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 配偶者 1/4、子 1/4 |
| 配偶者と直敬尊属 | 1/2 | 配偶者 2/6、直系尊属 1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者 1/2、兄弟姉妹 なし |
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者 1/2 |
| 子のみ | 1/2 | 子 1/2 |
| 直系尊属のみ | 1/3 | 直系尊属 1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | なし | なし |
※直系尊属:父母や祖父母などの自分より前の世代で、直通する系統の親族を指します。
具体的な遺留分の計算例
例えば、ある会社のオーナー経営者が亡くなり、相続人が配偶者と長男(後継者)、次男の3人だったとします。遺産総額が2億円(うち自社株式1億円)で、経営者が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残していたケースを考えてみましょう。
この場合、総体的遺留分は遺産全体の2分の1です。配偶者の法定相続分は2分の1、次男の法定相続分は4分の1なので、それぞれの個別的遺留分は、 ・配偶者:2分の1 × 2分の1 = 4分の1 ・次男:2分の1 × 4分の1 = 8分の1 となります。
つまり、配偶者は5,000万円(2億円×1/4)、次男は2,500万円(2億円×1/8)の遺留分を主張できる可能性があるのです。
▷関連:民法改正による新しい相続制度の概要|事業承継への影響も解説
遺留分侵害額請求とは
遺言などによって自分の遺留分が侵害された相続人は、財産を多く受け取った人(この例では長男)に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを求めることができます。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。かつては「遺留分減殺請求」と呼ばれ、現物(株式など)での返還が原則でしたが、法改正により金銭での支払いに一本化されました。
この請求権には時効があります。相続が開始したことと、自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年間、または何も知らなくても相続開始から10年間が経過すると、権利が消滅してしまいます。
▷関連:遺産分割対策で経営権の分散を防ぐ方法|相続・事業承継税制も解説
事業承継で遺留分が問題となるケース
遺留分の基本的な知識を押さえたところで、次に事業承継の場面で具体的にどのような問題が発生するのかを見ていきましょう。
後継者に株式を集中できないリスク
最大の懸念は、後継者への株式の集中が難しくなることです。遺留分を主張する他の相続人が現れると、会社の株式が分散してしまう恐れがあります。会社の所有権が分散すれば、経営の意思決定に時間がかかったり、株主間の意見対立で経営が停滞したりと、会社の安定性が大きく損なわれかねません。これはまるで、一隻の船の舵を複数人で握ろうとするようなもので、船は進むべき方向を見失い、迷走してしまうでしょう。
後継者の資金繰りが悪化するリスク
遺留分侵害額請求は金銭での支払いが原則です。つまり、後継者は他の相続人に対して、遺留分に相当する多額の現金を支払わなければならない可能性があります。会社の株式や事業用資産はすぐに現金化できるものばかりではありません。この支払いのために後継者個人の資産を切り崩したり、会社から多額の役員退職金を受け取ったりする必要に迫られ、結果として後継者自身の生活や、会社の運転資金を圧迫する深刻な事態に陥ることも考えられます。
株式分散による外部株主の混入リスク
遺留分侵害額請求により、後継者が一部の自社株を他の相続人に自社株で弁償することになった場合、その自社株を受け取った相続人が、外部の第三者に株式を売却する可能性があります。これにより、外部の投資家や他の株主が経営に影響を与えるリスクが生じ、後継者が安定した経営権の維持を困難にする場合があります。
相続人間での紛争(争族)のリスク
遺留分を巡る問題は、単なる法律やお金の問題にとどまりません。これまで仲の良かった家族が、相続をきっかけに対立し、感情的なしこりを残す「争族」へと発展するケースは少なくないのです。お金が絡むと、それまで抑えられていた不満や嫉妬が表面化しやすく、一度こじれると修復が困難なほどの深い溝が生まれてしまうこともあります。これは経営者(親)として、最も避けたいシナリオではないでしょうか。
事業承継税制の取消リスク
事業承継税制を利用して事業承継を行った場合、株式の分散には特に注意が必要です。遺留分侵害請求によって株式が分散し、後継者と同族関係者の議決権が50%を下回ったり、後継者以外の同族関係者が後継者の議決権を上回った場合、事業承継税制が取り消されてしまいます。事業承継税制の適用が取り消されると、その時点で猶予されていた多額の贈与税・相続税を後継者が負担することになります。
▷関連:事業承継税制とM&Aの関係|利点と欠点・要件・手続とは
事業承継における遺留分への具体的な対策
では、このような深刻な事態を避けるためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか。幸い、打つ手はいくつか存在します。

重要なのは、相続が始まってから慌てるのではなく、経営者が元気なうちに計画的に準備を進めることです。相続が発生した後では、取れる選択肢は非常に限られてしまいます。会社の未来と家族の幸せを守るためにも、先を見越した早めの行動が何よりも大切になります。
生前贈与を活用した対策
有効な対策の筆頭として挙げられるのが、生前贈与の活用です。
後継者への自社株式の贈与
計画的に後継者へ自社株式を贈与していくことで、相続財産そのものを減らし、将来の遺留分問題を緩和する効果が期待できます。ただし、生前贈与された財産も、一定の条件のもとで遺留分算定の基礎財産に含まれる点には注意が必要です。
また、自社株式の贈与には多額の贈与税が課される可能性がありますが、「特例事業承継税制」という制度を活用すれば、その納税が猶予されたり、最終的に免除されたりする場合があります。これは非常に強力な制度ですので、専門家と相談の上、活用を検討する価値は大きいでしょう。
後継者以外の相続人への財産贈与
一方で、後継者以外の相続人に対しても、生前に現金や不動産など、株式以外の財産を贈与しておくという方法も有効です。これは、将来の遺留分の支払いに備える「代償財産」を渡しておくという考え方です。あらかじめ他の財産で満足してもらえれば、会社の経営権を揺るがす株式の分散を避けられる可能性が高まります。
▷関連:株式贈与による事業承継|譲渡や相続との違い・メリット・流れを解説
遺言書を作成する
遺言書の作成も、基本的ながら非常に重要な対策です。「誰に」「どの財産を」「どれだけ相続させるか」を明確に記すことで、経営者の意思を法的な形で残すことができます。遺留分を完全に排除することはできませんが、相続トラブルの発生を抑制する効果は大きいでしょう。
特に重要なのが「付言事項」です。ここでは、なぜこのような財産分割にしたのか、後継者に会社を託す想いや、他の家族への感謝の気持ちなどを自分の言葉で綴ります。法的な効力はありませんが、残された家族の感情に訴えかけ、無用な争いを防ぐための潤滑油としての役割が期待できます。
遺留分の放棄
相続が開始する前に、相続人に自らの意思で遺留分を放棄してもらう方法もあります。ただし、これには家庭裁判所の許可が必要であり、本人からの自発的な申し立てが前提となります。経営者が放棄を強制することはできません。実際には、放棄をしてもらう代わりに一定の経済的な見返り(代償)を提供することが多く、その意味では他の対策と組み合わせながら進めることになるでしょう。
種類株式の利用
少し専門的なアプローチになりますが、種類株式を導入することでも対策が可能です。例えば、株式を「議決権のある株式」と「議決権のない株式(ただし配当は優先的に受け取れる)」の2種類に分けるといった方法があります。後継者には議決権のある株式を集中させて経営権を確保し、他の相続人には議決権のない株式を渡して配当で報いる、といった柔軟な設計が可能になります。
▷関連:種類株式とは?9つの内容を解説!事業承継・M&Aでの活用方法
生命保険の活用
生命保険の活用も、非常に有効な対策の一つです。経営者が亡くなった際に支払われる死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とみなされ、遺留分を計算する際の基礎財産には含まれません。この仕組みを利用して、後継者を死亡保険金の受取人にしておくのです。そうすれば、後継者は他の相続人から遺留分侵害額請求をされた際に、その保険金を支払いのための資金(代償資金)に充てることができます。会社の資産や個人資産に手を付けることなく、問題を解決できる可能性が生まれます。
M&Aによる第三者承継
親族内に適切な後継者が見つからない場合や、相続トラブルのリスクを根本から断ち切りたい場合には、M&Aによる第三者への事業承継も有力な選択肢となります。会社そのものを信頼できる第三者へ譲渡し、その対価として得た現金を相続財産とします。現金であれば、相続人間で公平に分割することが容易であり、株式の分散や評価額を巡る争いなど、遺留分に関するほとんどの問題を未然に防ぐことができます。
▷関連:事業承継とM&Aの違い|比較表・準備と流れ・メリットとデメット
遺留分に関する民法の特例(除外合意・固定合意)
中小企業の事業承継を後押しするため、「経営承継円滑化法」という法律に、遺留分に関する民法の特例が設けられています。これは非常に強力な対策となり得ますが、利用するには一定の要件を満たす必要があります。
除外合意とは
除外合意とは、後継者が先代経営者から贈与などによって取得した自社株式について、遺留分を計算する際の基礎財産から除外することを、推定相続人全員で合意する制度です。この合意には、全員の合意書に加えて、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要となります。ハードルは高いですが、認められれば株式を遺留分の対象から外せるため、絶大な効果を発揮します。
固定合意とは
固定合意とは、遺留分算定の基礎財産に含める自社株式の評価額を、合意した時点の評価額で固定(ロック)する制度です。これにより、後継者が会社を継いだ後の頑張りによって株価が上昇しても、その上昇分は遺留分の計算対象から外すことができます。後継者の経営努力が、他の相続人への遺留分支払額の増加に繋がるという理不尽な事態を避けられるメリットがあります。
特例を利用するための要件
これらの特例を利用するためには、会社が3年以上事業を継続していること、先代経営者が会社の代表者であったこと、後継者が会社の代表者であることなど、会社、先代経営者、後継者のそれぞれに定められた要件をクリアする必要があります。
▷関連:経営承継円滑化法とは?活用メリットと注意点を分かり易く解説
遺留分対策を進める上での注意点
これまで様々な対策を見てきましたが、これらを進める上ではいくつか心に留めておくべき注意点があります。
相続人とのコミュニケーション
どのような対策を講じるにしても、後継者以外の相続人への十分な配慮と、丁寧なコミュニケーションを欠かしてはなりません。なぜ後継者に会社を託したいのか、会社を存続させることが従業員や取引先、そして家族全員にとってどのような意味を持つのか、経営者自身の想いを真摯に伝えることが重要です。法的な手続きだけでなく、こうした血の通った対話こそが、無用な「争族」を避けるための最も大切な鍵となります。
対策には時間がかかる
生前贈与にせよ、民法の特例活用にせよ、いずれの対策も一朝一夕に実現できるものではありません。計画的に、そして長期的な視点で取り組む必要があります。事業承継や遺留分の問題は、いつか考えなければならない「先延ばしにできる課題」ではなく、今すぐにでも着手すべき「経営の最重要課題」の一つです。
専門家への早期相談
遺留分対策は、法律(民法、会社法など)や税金(相続税、贈与税など)の専門知識が複雑に絡み合います。経営者一人の判断で進めるのは非常に危険です。弁護士、税理士、公認会計士といった事業承継に詳しい専門家にできるだけ早い段階で相談し、自社の状況に合った最適なプランを一緒に練ってもらうことが、成功への何よりの近道です。
▷関連:事業承継の相談先を比較|中小企業のための選び方・おすすめ先を紹介
遺留分と事業承継のまとめ
事業承継における遺留分対策は、後継者への株式集中と経営権の安定に不可欠です。遺留分侵害額請求により資金繰りの悪化や株式分散、親族間紛争のリスクが生じます。生前贈与、遺言、生命保険の活用、民法の特例(除外合意・固定合意)、M&Aなどの対策がありますが、早期の準備と専門家への相談が成功の鍵です。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業M&Aに特化した豊富な実績を持つM&Aアドバイザー、公認会計士、税理士が多数在籍しています。遺留分対策を含む事業承継のサポートもワンストップで対応可能です。ぜひご相談ください。
完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >
著者

- 事業法人第二部長/M&A担当ディレクター
-
ヘルスケア分野に関わる経営支援会社を経て、みつきコンサルティングでは事業計画の策定、モニタリング支援事業に従事。運営するファンドでは、投資先の経営戦略の策定、組織改革等をハンズオンにて担当。東南アジアなど海外での業務経験から、クロスボーダー案件に関しても知見を有する。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修:みつき税理士法人
最近書いた記事
 2026年1月18日M&Aシナジー効果の評価方法|期待収益の算定と企業価値への反映
2026年1月18日M&Aシナジー効果の評価方法|期待収益の算定と企業価値への反映 2026年1月18日マイノリティ・ディスカウントとは?株価算定の仕組みと目安を解説
2026年1月18日マイノリティ・ディスカウントとは?株価算定の仕組みと目安を解説 2026年1月17日非流動性ディスカウントとは?M&Aの売却価格への影響と判例を解説
2026年1月17日非流動性ディスカウントとは?M&Aの売却価格への影響と判例を解説 2026年1月17日個人事業のM&Aでの売却は可能?相場・税金・事業譲渡の流れを解説
2026年1月17日個人事業のM&Aでの売却は可能?相場・税金・事業譲渡の流れを解説