人権デューデリジェンスとは、企業が事業活動における人権リスクを特定し、その防止・軽減を図る継続的なプロセスです。この記事では、人権デューデリジェンスが注目される背景や目的、具体的な進め方、そして買収(M&A)における重要性を平易に解説します。
「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」
そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。
> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ
税理士法人グループによる財務デューデリジェンス
M&Aに潜む財務リスク、見逃していませんか?
人権デューデリジェンスとは
近年、M&Aの検討において人権デューデリジェンス(人権DD)という言葉を耳にするようになりました。これは、企業が事業活動全体や、サプライチェーンにおいて人権侵害リスクを事前に確認し、そのリスクが顕在化しないように取り組むことを指します。企業が人権を尊重する責任を果たす上で不可欠な活動であり、社会的な要請がますます高まっています。
▷関連:デューデリジェンスとは|誰がやる?DDの意味をわかりやすく解説
法務デューデリジェンスとの違い
M&A(買収)における通常の法務デューデリジェンスは、主に譲受の対象企業に存在する事業リスクの把握を目的とし、買収実施の可否や契約内容の検討を考慮すれば足り、一度行えば足りるとされます。しかし、人権デューデリジェンスは性質が大きく異なります。

▷関連:デューデリジェンスの種類|法務・事業・環境・業界別M&Aも解説
人権デューデリジェンスは、具体的には以下の点が通常の法務デューデリジェンスと異なります。
- 目的: 人権デューデリジェンスの目的は、人権に及ぼしている負の影響の特定・把握と、その是正・救済です。これは、経営リスクではなく、人権侵害を受ける可能性のある人々(被害者または被害を受ける可能性のある者)の視点でリスクを考え、人権に負の影響を与えることを防止・軽減し、人権侵害が発生した場合には救済を提供することを目指します。
- 継続性: 人権デューデリジェンスは、一回に限るものではなく、繰り返し継続的に行うことが求められます。
- 対象リスク: 法令遵守だけでなく、法令を超えた国際基準への対応が必要です。
- 対象範囲: 対象企業とそのグループ会社だけでなく、サプライチェーンにおける人権侵害リスクにも対応が求められます。
- 主体性: 通常の人権デューデリジェンスは、専門家のアドバイスを受けつつも、各企業が主体的に行うことが期待されます。これは、事業自体の知見や経験が必要であり、人権侵害リスクを踏まえて事業上の意思決定と行動が求められるためです。
人権侵害リスクの具体例としては、各種ハラスメント、プライバシー問題、人種や性別などでの差別、表現や言論の自由の抑制、不当な労働条件(賃金未払い、残業過多など)、強制労働、児童労働、腐敗や汚職、賄賂などが挙げられます。
▷関連:法務デューデリジェンスでの契約書レビューとチェックポイントを解説
人権デューデリジェンスが注目される背景
近年、企業が人権デューデリジェンスに取り組むことへの社会的要請が急速に高まっています。この背景には、国際的な人権尊重の取り組みの進展と、それを受けた各国政府の動きがあります。
国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の策定
2011年に国連人権理事会において全会一致で承認された国連「ビジネスと人権に関する指導原則」 は、この分野における最も重要な文書の一つです。この指導原則は、国家が人権を保護する義務と、企業が人権を尊重する責任を明確にし、「保護、尊重、救済」という枠組みを提唱しました。これにより、企業は自らの事業活動によって引き起こされる、または助長される人権侵害への対応が求められるようになりました。
国内外の法制化の動向と企業への影響
国連による指導原則の策定後、人権デューデリジェンスに関する法制化の動きが国内外で活発になっています。
欧米における法制化の進展
欧米諸国では人権デューデリジェンスに関する法制化が先行しています。例えば、英国の2015年現代奴隷法やフランスの2017年企業注意義務法があります。EUでは、企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)案や強制労働産品禁止規則案が政治合意に至っており、企業に人権DD実施の必要性を生じさせています。
日本政府によるガイドライン策定と国内の動き
日本でも、政府や経済産業省、農林水産省が企業の取り組みを後押ししています。2020年には「ビジネスと人権に関する行動計画」が、2022年9月には「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が策定されました。これにより、公共調達に参加する企業にはガイドラインに沿った取り組みを行うよう努力義務が課されています。
世界情勢と人権デューデリジェンス
人権侵害リスクは、国内外を問わず様々な場面で生じ得ますが、近年の世界情勢は、特にリスクの高い地域での人権保護の要請を一層高めています。
紛争等の影響を受ける地域
日本政府ガイドラインでは、ミャンマーでのクーデターやロシアによるウクライナ侵攻、イスラエル・ガザ地区での紛争など、人権侵害リスクが高い地域における人権保護の要請の高まりを受け、こうした「紛争等の影響を受ける地域」で事業活動を行ったり、投資を行ったりしている企業に対し、強化された人権デューデリジェンスを実施するよう求めています。これは、企業が知らぬ間に紛争当事者の人権侵害行為に加担してしまう可能性を考慮したものです。なお、単に取引を停止したり事業から撤退したりするだけでなく、生活の糧を失う従業員への支援など、責任ある形で行うことが重要とされています。
▷関連:環境DDとは?M&Aでの目的・調査項目・流れ・費用相場と業者選定
企業が人権デューデリジェンスに取り組むべき理由
企業が人権デューデリジェンスに取り組むことは、現代社会において多岐にわたるメリットをもたらし、事業の持続可能性を高める上で重要です。
法的要請と国際基準への対応
前述のとおり、日本政府ガイドラインや国連指導原則といった国際基準に基づき、企業は人権デューデリジェンスの実施を求められています。特に、欧州における法制化の進展は、日本企業にも間接的に影響を与えます。これらの法的・国際的要請に応えることは、企業がグローバルサプライチェーンの中で事業を継続するために不可欠です。
レピュテーションリスクの軽減
人権侵害事案は、企業の存続を脅かす極めて重大な経営リスクとなり得ます。例えば、譲受した企業やそのサプライチェーンで強制労働が確認された場合、譲受企業自身が問題解決に取り組む責任を負うことになります。これは、補償ではカバーしきれないレピュテーションリスクや、人権侵害事案への対応コストの拡大に繋がる可能性があります。
事業継続における責任の履行
譲受後に人権侵害事案が発覚した場合、関係を断つことは推奨されず、人権状況の改善が求められます。これは、「ビジネスと人権」特有の考え方です。たとえ少数の株式取得にとどまる譲受であっても、人権侵害事案が放置されれば、適切な人権尊重の取り組みとは評価されません。人権デューデリジェンスにより事前にリスクを特定し対応することで、負の影響を防止・軽減し、企業の事業活動の安定に貢献できます。
M&Aにおける人権デューデリジェンス(人権DD)は、譲受企業が対象会社における人権侵害リスクを事前に特定・評価する調査です。
ESG評価と企業価値の向上
企業の人権尊重への取り組みは、ESG(環境・社会・ガバナンス)評価において重要な要素です。ESG評価が高い企業は、投資家から良い評価を得やすくなり、企業価値の向上に繋がる可能性があります。人権デューデリジェンスのプロセスや結果を公表し、情報開示を進めることは、投資家からの評価を高めるポイントになります。
▷関連:ESGデューデリジェンスとは?サステナビリティDDで企業価値向上
人権デューデリジェンスの基本的な実施プロセス
人権デューデリジェンスは、企業が人権リスクを特定し、防止・軽減するための重要なプロセスです。基本的な進行プロセスは以下のとおりです。
1 人権方針の策定
人権方針の策定は、企業が人権尊重への責任をどのように捉え、実践していくかを明確にするための第一歩です。経営トップが承認し、社内外に表明することが求められます。従業員、取引先、ビジネスパートナーなどに対し、どのような人権尊重を期待するのかを「方針」として明記し、一般に公開することが重要です。
人権方針策定の主要要件
人権方針の策定には、以下の5つの要件が重要とされています。
- 経営トップによる承認
- 社内外の専門家から人権に関する情報提供を受けている
- 従業員や取引先など関係者に対し、人権配慮への期待を明記している
- 一般に公開され、関係者に周知されている
- 企業全体の事業方針や手続に反映されている
2 人権への影響評価とリスクの特定
自社のビジネスプロセスを可視化し、潜在的な人権侵害リスクを洗い出し、特定します。すべてのリスクに対応することは現実的ではないため、「深刻度」と「発生可能性」の二つの軸で優先順位付けを行います。
リスクの深刻度の判断基準
人権リスクの深刻度は、以下の基準から判断されます。
- 規模: 人権の侵害による対象者への被害の大きさ
- 範囲: 被害を受ける、または影響を受ける可能性のある人数の多さ
- 救済困難度: 被害が生じた場合、影響を受ける前の状態に戻すことの難しさ
リスクの発生可能性の判断基準
人権リスクの発生可能性は、以下の要素から判断されます。
- 各企業の事業内容
- 法律体系や社会的慣行
- 救済措置の有無といった事業状況
人権リスクの洗い出しには、公表情報からの確認、現地調査、従業員へのヒアリング、アンケートの実施、専門家のサポートを受けることが有効です。特に人権保護の法制度が脆弱な新興国では、深刻な人権侵害が発生する可能性が高いとされています。
3 負の影響の防止・軽減と対応策の実施
特定された人権リスクの優先度に基づき、予防策と対応策を講じます。
教育・研修の実施
従業員の人権意識を高め、リスクに対する理解を深めます。
社内環境や制度の整備
人権尊重の企業文化を醸成するため、社内制度や環境を整備します。
サプライチェーンの管理と適切な対応
サプライチェーン全体における人権リスクを把握し、ガイドライン策定や監査の実施などを通じて適切な対応を行います。
これらの対策は、社内外の関係者が一体となって取り組むことが大切です。従業員に加え、必要に応じて取引先に対しても、実施目的や最終的な達成目標を共有し、共通認識のもと、取り組みを進められる体制を構築しましょう。
4 継続的なモニタリング
人権デューデリジェンスは、その継続性において真価を発揮する取り組みです。実施した施策の効果を定期的に検証し、人権状況の改善に貢献しているか、追加の対策が不要かといった観点から評価します。モニタリングには、自社の従業員やサプライヤーへのヒアリング、現場における監査などを通じて、施策の浸透度や現場の変化を客観的かつ公平に把握することが大切です。
4 ステークホルダーへの情報開示
内外のステークホルダーへの情報開示は、企業が果たすべき責務の一つです。重大な人権リスクが特定された場合、その内容、防止策、軽減策、講じた対策の評価について詳細な説明が求められます。主な情報公開の方法には、自社のウェブサイト、年次報告書、統合報告書、人権報告書などが挙げられます。これらの手段による透明性の高い情報開示は、企業の取り組みを示し、企業価値評価の向上に貢献します。
6 救済措置の設置・承継
被害者の救済は、企業による人権への負の影響を軽減し、回復させるためのプロセスです。救済を実現する方法として、以下の2つが考えられます。
相談窓口の設置
苦情処理メカニズムを確立し、人権侵害を受けた人々が声を上げやすい環境を整えます。
業界団体の苦情処理メカニズムの利用
専門知識を持つ第三者が介入することで、公正で透明性の高い解決が期待できます。
最適な手法はケースごとに異なりますが、被害を受けた対象者の心理を考慮し、検討することが重要です。譲受においては、対象企業が譲受前に救済を提供する責任を負っていた場合、譲受企業がその責任を引き続き負うことになります。
▷関連:人事・労務デューデリジェンスとは?M&Aでの調査項目・費用を解説
中小企業M&Aにおける人権DD
現状では、中小企業を対象とするM&Aにおいて人権DDが実施されることは限定的です。PwC Japanの調査によると人権DDの実施率は「実施していない」企業が56.2%を占めており、特に中小企業では時間、人材、財務のリソースが限られていることが課題となっています。これまでは財務DDや法務DDが中心で、人権DDは優先度が低く位置づけられてきました。
中小企業における人権リスクの実態
しかし、中小企業においても人権リスクは決して無縁ではありません。特に外国人技能実習生の問題は深刻で、過酷な労働条件や賃金未払い、適切な休憩時間が確保されないなど、技能実習生の待遇が不適切なケースが数多く報告されています。
製造業や建設業、農業などの分野では、労働力不足を補うため外国人技能実習生を受け入れる中小企業は多く、人権侵害のリスクが潜在的に存在します。このようなリスクは、M&A実行後に重大な風評被害や信用失墜、法的責任を招く可能性があります。
中小企業M&Aでの人権デューデリジェンスの必要性
近年、ESG投資の観点から企業の社会的責任への関心が高まっており、上場企業を中心に人的資本の開示も義務化されつつあります。中小企業であっても、大手企業のサプライチェーンに組み込まれている場合、人権リスクの管理が求められる可能性があります。M&Aにおいて人権DDを実施することで、譲受後の人権関連リスクを事前に把握し、適切な対応策を講じることができます。
▷関連:中小企業M&Aの財務デューデリジェンス|特有の論点と簡易財務DD
買収における人権デューデリジェンスの留意点
M&A(買収)局面における人権デューデリジェンスには、通常の法務デューデリジェンスとは異なる視点や留意点が存在します。譲受企業は、事前に人権侵害リスクを検証し、具体的な施策を検討・実行に関与することが期待されています。
買収前の検討段階
譲受企業は、買収を検討する段階から、対象企業やそのグループ会社、サプライチェーンにおいて重大な人権侵害事案が存在しないか、またそのリスクの高低を公表情報などから確認することが考えられます。報道等で事案(またはその疑い)が指摘されているかどうかに加え、企業の所在国・地域や産業によってリスクが高いと考えられる場合には、対象企業に対して情報開示を求める必要性が高まります。実際の買収過程において、人権状況に関する詳細な質問やQ&Aセッションがデューデリジェンスの各段階で行われることは多くありませんが、事前調査でリスクが高いと判断されるケースでは、特に公表情報の調査や資料開示の要請を丁寧に実施することが望まれます。
▷関連:海外M&Aのデューデリジェンスの注意点は?言語・法制度・文化の違い
最終契約の締結段階
現在のM&A実務では、対象企業が法令違反をしていないことの表明保証は広く行われていますが、人権侵害リスクへの対応という観点からは留意が必要です。
- 法令違反ではないが国際基準に違反する人権侵害事案はカバーされません。
- サプライチェーンにおける人権侵害事案はカバーされません。
人権侵害リスクが確認された場合には、具体的な人権侵害リスクを特定した上で、対象企業の認識の範囲で表明保証を求めることが考えられます。ただし、表明保証違反に対する補償だけでは人権状況の改善には繋がりません。そのため、譲受企業はコベナンツ(誓約事項)として、人権侵害事案に対応する義務を盛り込むことも重要です。
▷関連:表明保証条項の活用法|デューデリジェンス結果をM&A契約に活かす
買収後のPMIにおける対応
譲受後の経営統合(PMI)においても、人権デューデリジェンスは重要です。譲受後は、対象企業のサプライヤー等も含め、人権侵害リスクを将来にわたって防止・軽減していくことが求められます。対象企業が実施していた人権デューデリジェンスの結果を共有し、共に取り組みを進めることが望ましいです。従前の取り組みがなければ、譲受後に一から人権DDを行うことになります。人権DDは、採用、調達、製造、販売など、企業活動のあらゆる場面で生じ得るため、部門横断的な組織で検討を進めることが重要です。これにより、具体的な人権侵害リスクに関する情報や、実務上可能な対応策の検討が可能になります。
▷関連:PMIを成功させるデューデリジェンス|M&A後の統合リスク対策
税理士法人グループによる財務デューデリジェンス
M&Aに潜む財務リスク、見逃していませんか?
よくある質問|M&Aにおける人権デューデリジェンス(FAQ)
人権デューデリジェンスに関するよくある質問とその回答をまとめました。
人権デューデリジェンスとは、企業が事業活動を通じて発生し得る人権侵害リスクを特定し、その発生を防止・軽減するための継続的な取り組みです。これは、自社の直接的な活動だけでなく、サプライチェーン上の取引先や関連企業など、事業に関わる全ての人々や組織に対して行われる点が特徴です。国際的な人権尊重の高まりを受けて、企業に求められる責任の一つです。
日本政府のガイドラインは、国内で事業を行う全ての企業や個人事業主を対象としています。外国人技能実習生の強制労働問題など、日本企業が国内外で人権侵害リスクに直面する可能性は少なくありません。貴社の事業が人権侵害リスクの高い地域や産業に関わる場合、また、サプライチェーンにそうしたリスクが潜んでいる場合にも、関係があります。
人権デューデリジェンスを始める第一歩として、まず「人権方針の策定」が挙げられます。これは、企業が人権尊重責任をどのように果たしていくかを明確にし、社内外に公表するものです。次に、自社の事業プロセスやサプライチェーンにおける人権リスクを洗い出し、特定します。これらの取り組みは、社内全体で意識を共有し、必要に応じて外部の専門家からの助言を得ることも有効です。
サプライチェーンの人権問題とは、自社が直接関与していなくても、原材料の調達から製造、販売、廃棄に至るまでの過程で、取引先や委託先の企業、またはその従業員などにおいて発生する可能性のある人権侵害リスクを指します。例えば、新興国のサプライチェーンで強制労働が確認されるケースなどが考えられます。日本政府ガイドラインでは、譲受企業自身にもこうした問題への対応が求められています。
M&Aにおける人権デューデリジェンスのまとめ
人権デューデリジェンスは、企業が人権侵害リスクを見つけ、防止や改善、救済を行う継続的な取り組みです。国内外の法制度を受けて企業に求められており、ESG評価の向上やレピュテーションリスクの軽減、企業価値の向上につながる重要な経営課題です。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループとして15年以上の実績を持ち、財務調査に精通した公認会計士が在籍しています。税務を含めた専門的な調査をワンストップで提供します。財務デューデリジェンスをご検討の方は、お気軽にご相談ください。
完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >
著者
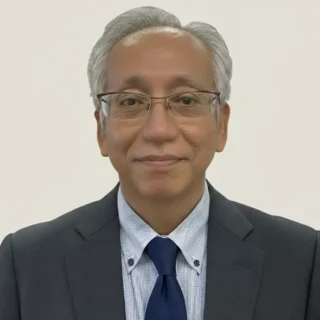
最近書いた記事
 2025年12月31日小売・飲食業M&Aのデューデリジェンス|店舗・FC・ブランド評価
2025年12月31日小売・飲食業M&Aのデューデリジェンス|店舗・FC・ブランド評価 2025年12月31日製造業M&Aのデューデリジェンス|工場・設備・サプライチェーン
2025年12月31日製造業M&Aのデューデリジェンス|工場・設備・サプライチェーン 2025年12月31日IT・ソフトウェア企業のM&Aデューデリジェンス|リスクと評価
2025年12月31日IT・ソフトウェア企業のM&Aデューデリジェンス|リスクと評価 2025年12月31日事業再生M&Aにおけるデューデリジェンスの実務ガイド
2025年12月31日事業再生M&Aにおけるデューデリジェンスの実務ガイド











