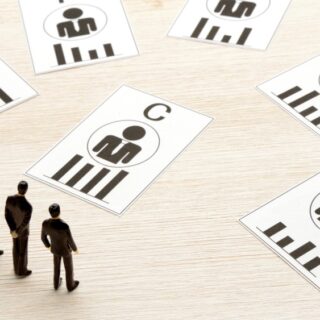M&Aは事業承継や会社の存続を左右する重要な選択肢です。本記事では「M&A なぜする」の疑問に、譲渡オーナーが実際に決断した背景や譲受企業との相乗効果まで、事例を交えて分かりやすく解説します。
「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」
そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。
> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

経営者がM&Aを決断する背景
ここ20年間で国内のM&A件数は右肩上がりに推移しています。2000年から2024年までの統計を眺めると、景気の波に揺らぎながらも全体的な増加傾向は明らかです。譲渡オーナーが「なぜ今なのか」と決断する裏には、後継者不足や業界構造の変化、そして個人的なライフプランの転換といった複数の要因が絡み合っています。本記事では、決断の主なトリガーを整理し、その後具体的な理由を掘り下げます。
譲渡オーナーが会社売却・企業譲渡を選ぶ理由
M&Aを検討する譲渡オーナーの動機は一つではありません。以下のように大別できます。
自社の発展を加速させるため
豊富な資金力や販路を持つ大手グループの傘下に入れば、中小企業が抱える「資本不足」「販路の狭さ」という壁を一気に乗り越えられます。技術力を活かし切れずにもどかしさを感じていた経営者ほど、シナジーを期待してM&Aを選択する傾向があります。
後継者不在を解消するため
日本の中小企業では少子高齢化による人材不足が深刻です。親族に後継候補がいても社外でキャリアを積んで戻らないケースや、育成期間中に意思が揺らぐケースも珍しくありません。株式譲渡によって経営権を譲受企業へ渡せば、従業員の雇用と取引先との関係を守りながら事業を次世代へつなげられます。
親族内承継が頓挫した事例
創業五十年目を迎えたA社では、二代目社長が東京勤めの長男を呼び戻し五年間育成しました。しかし長男は責任の重さに耐えきれず再び東京へ戻りたいと告げます。長女も子育てを理由に辞退し、番頭候補も不在。時間的猶予が限られるなかで第三者への承継としてM&Aを選択し、近隣の譲受企業と合意しました。
▷関連:会社を売りたい|最短で進める準備7項目・手順・必要書類・注意点
自身や家族の健康・介護への備え
譲渡オーナー自身が高齢で体調に不安を抱える場合や、親族の介護が必要になる場合、経営の最前線に立ち続けることは難しくなります。「会社の調子は良いのに自分の体がついていかない」と感じた瞬間が決断のタイミングです。業績が維持できていれば譲受企業の選択肢も広がり、条件交渉を有利に進められます。
早期引退で第二の人生を楽しむため
モチベーションの低下や「別の人生を歩みたい」という思いから、40代・50代でアーリーリタイアを目指す経営者もいます。事業が成長軌道に乗っているうちに譲渡することで、高い対価を確保し、趣味や社会貢献活動に時間を使えるようになります。譲渡後に子会社社長として一定期間残るパターンもあり、段階的な引退が可能です。
国内外への移住を見据えて
日本を離れ海外に生活拠点を移す計画を立てると、距離と時差の壁が経営判断を鈍らせます。遠隔経営のリスクを避けるため、同業の譲受企業へ経営権を譲る決断が行われます。社員の雇用継続と取引先の契約維持を譲受企業が保証できれば、移住後も心配なく生活基盤を築けます。
ノンコア事業を切り離し集中と選択を進める
いわゆるカーブアウトによるM&Aを図るものです。経営資源は有限です。不採算部門が資金と人材を食いつぶしているなら、いくら汗を流しても利益は漏れていきます。子会社株式の譲渡・事業譲渡でノンコア事業を手放すと、黒字部門への投資が一気に加速し、営業現場の士気も上がります。「無駄な荷物を下ろして身軽になる」イメージです。
不採算事業を切り離すため
複数の事業を抱える企業では、一部門の赤字が全体の資金繰りを圧迫します。赤字事業だけを事業譲渡すれば、経営資源を成長部門に集中できるため、財務体質が改善します。譲渡価格が低くても継続的な損失を止める効果は大きく、結果として黒字部門の企業価値を守ることにつながります。
シナジーを生み出す拡大戦略
譲渡オーナー自身が「さらなる飛躍の舞台を求めたい」と感じるケースもあります。たとえば自転車レンタル事業のG社は、駅から遠い賃貸物件に付加価値を付けるべく、自転車サービスを組み込む構想を持つ譲受企業からオファーを受けました。住宅と自転車という異色の組合せが奏功し、地域の移動インフラを刷新するモデルとして注目を集めています。
資金調達と新規投資を目的にした譲渡
急速な設備投資や大規模なマーケティング展開には多額の資金が欠かせません。金融機関からの借入では担保や個人保証の負担が重く、資金調達スピードも遅れがちです。経営者がタイミングを逃さずに次の一手を打つため、譲渡対価や第三者割当増資でまとまった資金を確保し、リスクを抑えた形で事業拡大に乗り出すケースが増えています。
開発資金を得る第三者割当増資
「革新的な製品を形にしたいが自己資金では足りない」——そんなときに有効なのが第三者割当増資です。株式を引き受ける譲受企業は、開発成果を自社の技術ポートフォリオに組み込めるメリットがあるため、出資と同時に販路提供や技術協力を行うケースが多いです。ただし持株比率が想定以上に変動すると経営権を失うリスクがあるため、発行株数や議決権構成のシミュレーションが不可欠です。
エグジットと再投資
いわゆるシリアルアントレプレナーは、成長途中で高値売却を実現し、その資金を次の事業へ投入することで連続起業を実践しています。これによりリスクを限定しながら挑戦と撤退を高速回転させる“起業家の新陳代謝”が生まれます。
代理経営に限界を感じたとき
経営経験の浅い家族が代表に就く場合、意思決定の重圧と専門知識不足が経営を停滞させます。「自分が守るより、プロに託したほうが社員の未来は明るい」、「雇用を守りたいが自分には荷が重い」と感じたときが譲渡のタイミングです。譲受企業が経営インフラを提供し、代理社長は相談役へ退く——そんな形で従業員の生活を守った案件も多く報告されています。また、譲受企業が経営ノウハウと市場ネットワークを持ち込むことで、従業員のキャリアパスが広がる例も多く見られます。
会社存続と企業再生のためのM&A
数期連続の赤字や負債過多で銀行融資が伸びない企業でも、技術や顧客基盤を評価する譲受企業が現れれば再生の可能性が開けます。株式譲渡でグループ入りすれば、販路の共有や人員の再配置で黒字転換が狙えます。ポイントは「再生可能」と判断してもらえるだけのコア技術や地域シェアを残しておくことです。
赤字が続き金融支援が受けづらくなった場合でも、ノウハウや顧客基盤が魅力的であれば譲受企業は現れます。買収後に人的・資金的リソースを注入し再成長をめざす「企業再生型M&A」は、従業員の雇用と取引先との取引を守る観点でも意義深い手法です。
再生可能性を示すために必要なこと
譲渡オーナーがまず取り組むべきは、赤字部門の原因分析と可視化です。構造的なコスト高か、単一顧客依存か、設備老朽化か——要因を切り分ければ、譲受企業は改善シナリオを描きやすくなります。またデューデリジェンスで“隠れ負債”が露見しないよう、簿外債務や未収金の精査を先回りして行うことも信頼獲得の鍵となります。
▷関連:債務超過でもM&Aできる!赤字企業の2割が売却を検討・私的整理
譲受企業が何故M&Aをするのかも理解する
譲渡オーナーが安心して会社を託すためには、譲受企業のメリットも把握しておく必要があります。
既存事業を強化できる
技術・販路・ブランド認知――足りないピースを外部調達し、自社リソースと組み合わせることで相乗効果が生まれます。例えば製造業が物流会社を譲受してサプライチェーンを内製化し、コストと納期を同時短縮する例が典型です。IT企業がデザイン会社を譲受するなど、組合せは多様です。
スケールメリットを獲得できる
規模拡大により資材の一括調達や広告費の削減が可能となり、利益率が向上します。金融機関からの評価も向上し資金調達コストも低下します。譲受企業がこれらのメリットを見込めるほど、譲渡オーナーにとっても好条件の提示が期待できます。なお、ブランド力が増すことで採用活動も優位に働き、人材獲得競争で有利になります。
新規事業へ迅速に参入できる
ゼロから事業を立ち上げるより、既に顧客と実績を持つ企業を譲受した方が時間とコストを大幅に節約できます。これは譲受企業が提示する対価を押し上げる要因となり、譲渡オーナーに有利な交渉材料を提供します。
既に収益モデルが確立された事業を取得すれば、ゼロスタートに比べ初期投資・立ち上げ期間・人材採用コストを大幅に削減できます。これはベンチャー企業だけでなく、成熟企業が成長ドライバーを求めて買収に動く大きな動機です。
▷関連:M&Aを学ぼう!経営者が知っておきたい知識・勉強方法を紹介
M&A・会社売却・企業譲渡を決断する際のポイント
中小企業のオーナー経営者がM&Aをすると決心するまでの重要な考慮事項を紹介します。
決断のタイミングを見極める指標
M&Aは“最後の逃げ道”ではありません。むしろ業績が伸びている段階でこそ高い評価が付き、好条件で交渉が進みます。そこで以下の3つを経営者自身で定期的にチェックすることを推奨します。
- EBITDAの成長率が停滞したとき:利益率低下の兆しを示す赤信号
- 後継者候補の確定時期:承継プランが固まらない場合はM&Aを選択肢に
- 主要顧客構成の変化:特定顧客依存が進む前に販路拡大策としてM&Aを検討
これらの指標が“黄信号”を点滅させたら、譲渡すべき可能性が生じていますので、仲介会社へ早期相談することで選択肢が広がります。
▷関連:最適なM&Aのタイミングはいつ?高値で会社を売るポイント・注意点
M&A成功の鍵は“準備”と“覚悟”
高値売却のための財務体質改善、買い手を引きつける事業計画の可視化、従業員への情報開示タイミングなど、やるべきことは多岐にわたります。しかし最も大切なのは、譲渡オーナー自身が「会社の未来に最善を尽くす」という覚悟を固めることです。覚悟ができた瞬間、専門家と協働する作業は驚くほど円滑に進みます。
M&A後のキャリアとライフプラン
譲渡オーナーの中には、クロージング後に子会社社長や顧問として一定期間残り、経営移行をサポートするパターンがあります。期間満了後はセミリタイアで地方移住、社会貢献活動、スタートアップ投資など、第二のキャリアを自由に設計できます。「譲渡で得た資金」と「自由な時間」という二つの資産をどう配分するかが、今後の充実度を左右します。
決断を後押しする感情と覚悟
最後に忘れてはならないのが、数字では測れない「感情」の部分です。譲渡オーナーは社員への責任感や長年培ったブランドへの愛着に揺れながら決断します。「会社を育てたのは自分だが、次に花を咲かせるのは譲受企業だ」と腹をくくる瞬間には、不思議と肩の荷が下りたような安堵が訪れます。経営のバトンを託すとは、過去への感謝と未来への期待を同時に抱く行為なのです。
▷関連:M&Aでの社長の役割とは?譲渡の時期・方法・条件・雇用・PMI
みつきコンサルティングがM&A仲介した会社売却の事例
みつきコンサルティングは、これまで500件を超えるごM&Aを支援してまいりました。公認会計士・税理士ら専門家チームが、完全成功報酬制で支援した成約事例から、会社を売却した事例をご紹介します。
人材難を医療プラットフォーム企業との統合で解決

譲渡企業:医薬品開発支援(売上約2億円)
譲受企業:医療コンテンツ(売上約100億円)
スキーム:株式譲渡
創業20年のCROが人材不足と大手との競争激化を背景に、医療情報プラットフォームを持つ異業種企業への譲渡を決断。デジタル技術との融合で新たな治験サービスを創出。
創業70年の電気工事を全国プラント大手へ承継

譲渡企業:電気設備工事(売上約5億円)
譲受企業:建機レンタル(売上約180億円)
スキーム:株式譲渡
老舗の電気設備・プラント設備工事会社が後継者不在と人材確保課題を背景に、同業プラント大手グループへの承継を決断し、従業員雇用継続と事業基盤強化を実現。
上記は当社のM&A仲介実績のほんの一部です。様々な業界・規模の成約事例を下記のページでご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
その他の事例に学ぶ会社を売却する理由のリアル
実際の相談には、数字だけでは読み取れない切迫感や人間ドラマが存在します。
産業廃棄物業H社の人材不足問題
H社は産業廃棄物処理を地域で担う重要な事業者でしたが、慢性的な人材不足で後継者育成が進まず、社長は70代に。廃業すれば地域インフラに穴が空くため選択肢は限られます。最終的に人員が豊富で隣接エリアをカバーする譲受企業とM&Aが成立し、従業員も引き続き地域に貢献できる環境が整いました。
イベント運営会社K社の環境激変
新型コロナウイルスの影響で売上が急減したK社は、譲受企業の資金力とネットワークを得て一年後に収益が1.5倍へ回復しました。危機のさなかでも「会社を守り、雇用を守る」という社長の強い意志が、適切なタイミングでの譲渡につながりました。
赤字事業を譲渡したN社の例
複数事業を営むN社では、一部門が三期連続で赤字。黒字部門が補填し続ける状況は、社長の精神的負担も大きいものでした。M&A仲介を通じて赤字部門だけを譲渡すると、翌期には資金繰りが大幅に改善。残された従業員にも積極的な設備投資が行われ、黒字部門の売上が二割伸びました。
会社売却・企業譲渡する理由のまとめ
M&Aは後継者不在や資金調達、事業再生など多様な課題を一手に解決し、会社と従業員の未来を守る選択肢です。本記事では譲渡オーナーが「なぜM&Aをするのか」を実例と共に紐解きました。決断の鍵はタイミングと準備、そして覚悟です。
当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。
完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >
著者

- 事業法人第四部長/M&A担当ディレクター
-
国内証券会社(現SMBC日興証券)にてクライアントの資産運用を支援。みつきコンサルティングでは、消費財・小売業界の企業に対してアドバイザリーを提供。事業承継案件のみならず、Tech系スタートアップへの支援も行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修:みつき税理士法人
最近書いた記事
 2025年12月10日スタートアップによるM&A|イグジット・IPO前のバイアウト戦略
2025年12月10日スタートアップによるM&A|イグジット・IPO前のバイアウト戦略 2025年11月30日社長の後継者がいない会社|後継ぎ募集の理由・事業承継方法を解説
2025年11月30日社長の後継者がいない会社|後継ぎ募集の理由・事業承継方法を解説 2025年11月30日経営者のハッピーリタイアとは?事業承継M&Aをわかり易く解説
2025年11月30日経営者のハッピーリタイアとは?事業承継M&Aをわかり易く解説 2025年11月29日黄金株とは?中小企業が事業承継に活用できる種類株!発行方法も解説
2025年11月29日黄金株とは?中小企業が事業承継に活用できる種類株!発行方法も解説