事業再生M&Aは、経営不振に陥った企業を譲受して再建する手法です。デューデリジェンスでは、窮境原因の特定や再生計画の実現可能性評価など、通常のM&Aとは異なる視点が求められます。本記事では、中小企業のオーナー経営者が理解すべき、事業再生M&Aにおけるデューデリジェンスの要点を解説します。
「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」
そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。
> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ
税理士法人グループによる財務デューデリジェンス
M&Aに潜む財務リスク、見逃していませんか?
デューデリジェンス(DD)とは
デューデリジェンスは、M&Aにおいて譲受企業が譲渡企業に対して実施する詳細な調査のことです。対象企業の事業内容、財務状態、法務リスク、人事組織など、あらゆる側面を調査し、潜在的なリスクや課題、将来の成長可能性を把握します。この調査結果に基づいて、譲受企業は最終的な譲受価格や契約条件を決定し、M&Aを実行するかどうかの判断を行います。
▷関連:デューデリジェンスとは|誰がやる?DDの意味をわかりやすく解説
財務DDの重要性
財務デューデリジェンスは、デューデリジェンスの中でも特に重要な要素です。譲渡企業の財務状況を詳細に分析し、過去の業績や将来の収益性、資産と負債の状況を調査します。これにより、財務的なリスクやM&A後の統合プロセスにおける課題を早期に発見できます。特に事業再生M&Aでは、財務状況の正確な把握が成否を分けるポイントとなります。
▷関連:財務デューデリジェンスとは?M&Aでの目的・手順・調査項目・費用
事業再生M&Aの位置づけ
一般的な中小企業の事業承継や同業他社の譲受とは異なり、事業再生M&Aはより複雑な要素や固有のリスクを伴います。経営状況が悪化している企業を対象とするため、通常のM&Aでは見られない特殊な課題に直面します。そのため、デューデリジェンスの目的やスコープを対象企業の特性に合わせて調整することが不可欠です。
事業再生M&Aの特徴とリスク
事業再生M&Aは、経営不振に陥った企業を譲受し、再建を目指す取引です。通常のM&Aと比べて、対象企業が抱える問題の深刻さや複雑さが大きく異なります。
経営不振企業に特有の課題
経営不振企業では、財務体質の悪化だけでなく、従業員の士気低下、取引先との信頼関係の毀損、経営管理体制の不備など、多岐にわたる問題が複合的に発生しています。これらの課題を正確に把握し、再生の可能性を見極めることが重要です。単に財務数値を分析するだけでは不十分で、事業の本質的な問題点を特定する必要があります。
高リスク・高リターンの投資
事業再生M&Aは、リスクが高い一方で、成功すれば大きなリターンを得られる可能性があります。通常よりも低い価格で譲受できる機会がある反面、再生に失敗すれば投資資金を回収できないリスクも抱えています。この特性を理解した上で、デューデリジェンスを通じてリスクとリターンを慎重に評価することが求められます。
▷関連:デューデリジェンスの種類|法務・事業・環境・業界別M&Aも解説
事業再生M&AにおけるDDの重点項目
事業再生M&Aのデューデリジェンスでは、通常のM&Aとは異なる視点と手法が必要です。以下、重点的に調査すべき項目を詳しく解説します。
窮境原因の徹底的な分析
事業再生M&Aにおいて最も重要なのは、対象企業がなぜ経営不振に陥ったのかという窮境原因を徹底的に分析することです。原因を正確に特定できなければ、適切な再生計画を立てることができません。
外部要因の調査
窮境原因には、事業環境の変化や競合激化といった外部要因があります。市場の縮小、技術革新による陳腐化、新規参入による競争激化など、企業を取り巻く環境の変化を詳細に分析します。これらの外部要因が一時的なものか、構造的な変化かを見極めることが重要です。外部要因が主因の場合、企業自体の競争力は残っている可能性があり、環境の変化に適応できれば再生の余地があります。
内部要因の特定
内部要因には、非効率な事業運営、過剰な債務、不正行為などが含まれます。過度な設備投資、過大な在庫、放漫経営、不適切な資金調達などを調査します。過去の財務諸表を詳細に分析し、経営判断の誤りや管理体制の不備を特定します。内部要因が主因の場合、経営体制の刷新や業務プロセスの改善により、再生できる可能性があります。
原因究明の手法
窮境原因の究明には、決算書の時系列分析、経営者や従業員へのヒアリング、取引先や債権者への聞き取り、業界動向の調査などを組み合わせます。過去5年から10年程度の財務データを分析し、どの時点でどのような問題が発生したかを特定します。また、必要に応じて不正調査を実施し、粉飾決算や横領などの不正行為の有無を確認します。
▷関連:事業DDとは?目的・調査項目・進め方・コンサル活用を解説
事業再生計画の実現可能性評価
事業再生M&Aでは、対象企業の再生に向けた事業再生計画が策定されることが一般的です。この計画が現実的に実現可能かどうかを厳しく評価する必要があります。
計画の前提条件の検証
再生計画の前提となっている市場環境、売上予測、コスト削減の実現可能性などを詳細に検証します。過度に楽観的な想定や根拠のない数値目標がないか、慎重に確認します。市場シェアの拡大を前提とする場合、その実現手段が具体的に示されているか、競合の動向を踏まえているかなどを評価します。
収益改善策の妥当性
売上増加施策やコスト削減策が、実現可能で具体的な内容になっているかを確認します。単なる希望的観測ではなく、具体的なアクションプランと実行体制が整っているかを評価します。例えば、新商品の投入による売上増を見込む場合、その商品の市場性や競争力、必要な投資額などを詳細に検討します。コスト削減についても、単なる人員削減だけでなく、業務効率化の具体策が示されているかを確認します。
資金調達計画の実現性
再生計画の実行には、運転資金や設備投資資金が必要です。これらの資金をどのように調達するのか、計画が具体的で実現可能かを評価します。金融機関からの追加融資が前提となっている場合、その可能性を債権者との関係も含めて慎重に判断します。M&A後に譲受企業が資金を供給する場合、その金額や時期が適切かを検討します。
資金繰りと運転資金の評価
経営不振に陥っている企業では、資金繰りが逼迫しているケースが多く見られます。現在の資金繰り状況や将来的な資金ショートのリスクを詳細に調査することが不可欠です。
現状の資金繰り分析
直近の現預金残高、月次の収支状況、支払いの遅延状況などを詳細に把握します。支払手形の期日管理、買掛金の支払状況、従業員給与の支払状況なども確認します。資金繰り表を作成し、今後3か月から6か月程度の資金の過不足を予測します。特に、M&A実行までの期間に資金ショートのリスクがないかを慎重に評価します。
運転資金の必要額算定
事業を継続するために必要な運転資金の規模を算定します。売掛金、在庫、買掛金のサイクルを分析し、通常時と比較して資金需要がどの程度増加しているかを確認します。経営不振企業では、取引先の信用不安から前払いを求められるなど、運転資金需要が増大している場合があります。M&A後に正常化するまでに必要な資金額を見積もります。
キャッシュマネジメント体制
M&A実行後のキャッシュマネジメントが適切に行えるかを評価します。日次での資金管理体制、資金計画の策定と見直しプロセス、経営者への報告体制などを確認します。再生期間中は、通常以上に厳格な資金管理が求められるため、その実行体制が整備できるかを見極めます。
債権者との関係調査
事業再生M&Aにおいては、対象企業の債権者との関係も重要なデューデリジェンス項目です。債権者の理解と協力なくして、再生を成功させることはできません。
金融債務の状況
金融機関からの借入状況、返済条件、担保設定の有無などを詳細に調査します。リスケジュール(返済条件の変更)を実施している場合、その内容と今後の返済計画を確認します。複数の金融機関から借入がある場合、各行の対応姿勢や債権者間の力関係も把握します。メインバンクがどこか、支援に積極的かなども重要な情報です。
債権者との合意形成
M&A実行にあたり、債権者との間でどのような合意が必要か、その実現可能性を評価します。債務免除やDDS(デット・デット・スワップ)、債務の株式化(DES)などが必要な場合、債権者が応じる可能性があるかを慎重に判断します。既に債権者会議が設置されている場合、その運営状況や合意形成のプロセスも確認します。
仕入先や取引先との関係
金融機関以外の債権者との関係も重要です。仕入先への未払金の状況、取引条件の変更(現金払いへの移行など)の有無を確認します。取引先の信用不安により、仕入れが困難になっていないか、代替の仕入先を確保できるかなども評価します。M&A後に取引関係を継続できるかが、事業再生の成否を左右することもあります。
▷関連:法務デューデリジェンスでの契約書レビューとチェックポイントを解説
法的整理と私的整理の対応
事業再生は、法的整理と私的整理の大きく二つのスキームがあります。どちらのスキームで再生を進めるかによって、デューデリジェンスで留意すべきポイントが異なります。
法的整理の場合
民事再生法や会社更生法などの法的整理の場合、裁判所の手続が中心となります。再生計画案の認可要件、債権者の同意要件などを確認します。法的整理では、手続の透明性が高い反面、対外的な信用が大きく低下するリスクがあります。既に法的整理の手続中である場合、裁判所への提出書類や再生計画案の内容を精査します。
私的整理の場合
事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)や特定調停などの私的整理の場合、債権者との個別交渉が中心となります。主要債権者の同意が得られる見込みがあるか、一部債権者の反対で計画が頓挫するリスクがないかを評価します。私的整理では、対外的な信用低下を抑えられる一方、全債権者の合意形成が困難な場合があります。
スキーム選択の妥当性
対象企業の状況に照らして、選択されている整理スキームが適切かを評価します。債務の規模、債権者の数と属性、事業の継続可能性などを総合的に判断します。必要に応じて、スキームの変更や併用を検討することもあります。スキームの選択は、M&Aの実現可能性やM&A後の事業運営に大きな影響を与えます。
▷関連:法務DDとは?M&Aでの進め方・弁護士の費用相場・調査項目を解説
不正調査の必要性と実施方法
経営不振の原因が、過去の不正行為や粉飾決算にある可能性も否定できません。事業再生M&Aにおいては、不正行為が隠蔽されているリスクが高く、慎重な調査が必要です。
フォレンジック調査の実施
不正調査(フォレンジック調査)では、会計帳簿の詳細な分析、異常取引の抽出、関係者へのヒアリングなどを実施します。粉飾決算の手法として、架空売上の計上、在庫の過大評価、費用の繰延べなどが行われていないかを確認します。電子データの解析により、改ざんや削除の痕跡を検出することもあります。
不正の影響額の特定
不正行為が発見された場合、その影響額を正確に算定します。修正後の財務諸表を作成し、実際の財務状態や経営成績を把握します。不正による影響が大きい場合、M&Aの条件や実行の可否に重大な影響を与えます。また、不正に関与した者の特定と、その者の処遇についても検討が必要です。
再発防止策の評価
過去に不正行為があった場合、同様の問題が再発しないような管理体制の構築が不可欠です。内部統制の整備状況、経営者の意識、コンプライアンス体制などを評価します。M&A後に、どのような管理体制を導入すべきかを計画に盛り込みます。
事業再生M&Aのデューデリジェンス実施体制
事業再生M&Aのデューデリジェンスを成功させるには、適切な専門家チームの組成と効率的なプロジェクト管理が重要です。
適切な専門家の選定
事業再生M&Aのデューデリジェンスでは、通常のM&A以上に高度な専門性が求められます。公認会計士や税理士による財務調査、弁護士による法務調査に加えて、企業再生の実務経験を持つ専門家の参画が不可欠です。
倒産法制や再生手続に精通した弁護士、企業再生コンサルタント、事業評価に強い公認会計士など、それぞれの分野で豊富な経験を持つ専門家を選定します。また、不正調査が必要な場合は、フォレンジック調査の専門家も加えます。専門家の選定にあたっては、過去の実績や専門分野を十分に確認することが重要です。
▷関連:デューデリジェンスの専門家|依頼業者の選び方・役割・費用を解説
調査スコープの設定
デューデリジェンスの調査範囲は、譲受企業のM&A戦略やリスク許容度に応じて調整します。事業再生M&Aでは、対象企業が抱えるリスクが通常よりも高いため、リスクの高い項目については詳細な調査が必要です。
一方で、限られた時間と予算の中で効率的に調査を進めるため、優先順位を明確にすることも重要です。窮境原因の分析、資金繰りの評価、債権者との関係調査など、事業再生特有の重要項目に重点を置きます。リスクが低いと判断される項目については、簡易的な調査に留めることで、全体の効率を高めます。
▷関連:DDのスコープ設定|M&Aの目的と予算に応じた調査範囲を解説
調査期間とスケジュール管理
事業再生M&Aでは、対象企業の財務状況の悪化により、迅速な意思決定が求められることがあります。一方で、通常のM&A以上に詳細な調査が必要なため、期間とのバランスが重要です。
調査開始前に、全体のスケジュールと各段階での成果物を明確にします。調査の進捗状況を定期的に確認し、必要に応じてスコープの調整やリソースの追加を行います。特に、資金繰りが逼迫している場合は、M&A実行までの期間が限られるため、効率的な調査が求められます。
税理士法人グループによる財務デューデリジェンス
M&Aに潜む財務リスク、見逃していませんか?
よくあるご質問|事業再生M&Aでのデューデリジェンス(FAQ)
事業再生M&Aのデューデリジェンスに関して、よく寄せられる質問にお答えします。
事業再生M&Aのデューデリジェンスでは、まず経営が悪化した原因である「窮境原因」を徹底的に分析します。事業の問題なのか、財務的な問題なのか、経営管理体制に問題があるのかなど、原因を特定することが再生への第一歩です。
次に、策定された事業再生計画が本当に実行できる計画なのかを厳しく評価します。そして、資金繰りがどのくらい逼迫しているのか、M&A後に必要な資金はいくらかといった資金繰りやキャッシュマネジメントに関する調査が非常に重要です。また、過去の経営における不正行為の有無を調査することも必要になる場合があります。
M&Aにおけるデューデリジェンスでは、公認会計士や税理士、弁護士などの専門家チームを組成するのが一般的です。事業再生M&Aにおいては、これらに加えて、企業の再生実務や倒産法に詳しい専門家、フォレンジック調査に強い専門家といった、対象企業の特性に合わせた専門家を選定することが成功の鍵となります。
特に、企業再生の経験が豊富な専門家は、窮境原因の分析や再生計画の評価において、実践的な視点からアドバイスを提供できます。専門家の選定にあたっては、過去の案件実績や専門分野を確認し、自社のM&A案件に適した人材を選ぶことが重要です。
事業再生M&Aのデューデリジェンスの期間は、対象企業の規模や複雑さ、調査スコープによって異なります。一般的には、1か月から3か月程度を要することが多いです。ただし、資金繰りが逼迫している場合など、迅速な意思決定が求められる状況では、短期間で調査を完了させる必要があります。
調査期間を短縮するには、事前に調査スコープを明確にし、優先順位の高い項目に集中することが重要です。また、対象企業からの資料提供が円滑に進むよう、必要書類のリストを早期に提示し、協力体制を構築することも効果的です。
デューデリジェンスの費用は、調査範囲、専門家の人数、調査期間などによって大きく異なります。中小企業の事業再生M&Aの場合、数百万円から1000万円程度が一般的な相場です。ただし、大規模な企業や複雑な案件では、それ以上の費用がかかることもあります。
費用を適切に管理するには、調査開始前に専門家と費用の見積もりを詳細に協議し、予算の範囲内で最大の成果が得られるよう調査スコープを設定することが重要です。また、調査の進捗に応じて追加調査が必要になる場合もあるため、ある程度の予備費を確保しておくことも検討すべきです。
事業再生でのデューデリジェンスのまとめ
事業再生型M&Aでは、通常とは異なる固有のリスクや課題があります。デューデリジェンスでは、対象企業の特性に合わせて調査内容を調整することが不可欠です。窮境原因の分析や再生計画の実現可能性、資金繰りなどが重要な調査項目となります。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループとして15年以上の実績を持ち、財務調査に精通した公認会計士が在籍しています。税務を含めた専門的な調査をワンストップで提供します。財務デューデリジェンスをご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >
著者
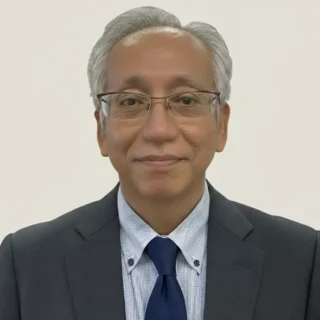
最近書いた記事
 2025年12月31日小売・飲食業M&Aのデューデリジェンス|店舗・FC・ブランド評価
2025年12月31日小売・飲食業M&Aのデューデリジェンス|店舗・FC・ブランド評価 2025年12月31日製造業M&Aのデューデリジェンス|工場・設備・サプライチェーン
2025年12月31日製造業M&Aのデューデリジェンス|工場・設備・サプライチェーン 2025年12月31日IT・ソフトウェア企業のM&Aデューデリジェンス|リスクと評価
2025年12月31日IT・ソフトウェア企業のM&Aデューデリジェンス|リスクと評価 2025年12月31日事業再生M&Aにおけるデューデリジェンスの実務ガイド
2025年12月31日事業再生M&Aにおけるデューデリジェンスの実務ガイド











