ESGデューデリジェンスとは、環境・社会・企業統治の観点から対象企業のリスクや機会、新たなビジネスチャンスを評価する手続です。この記事では、ESGデューデリジェンスの具体的な進め方や評価ポイント、そして企業価値向上への寄与について詳しく解説します。
「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」
そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。
> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ
税理士法人グループによる財務デューデリジェンス
M&Aに潜む財務リスク、見逃していませんか?
ESGデューデリジェンスとは
ESGデューデリジェンス(DD)とは、M&Aにおいて投資対象企業の環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)に関するリスクと機会を調査・分析する手続です。非財務情報を評価し、企業価値の向上や将来のリスク回避に活用します。
▷関連:デューデリジェンスとは|誰がやる?DDの意味をわかりやすく解説
ESG経営の拡がり
近年、投資家や企業にとって、環境(E:Environmental)、社会(S:Social)、企業統治(G:corporate Governance)の観点が非常に重要になっています。ESGという言葉が誕生してまだ10数年しか経っていませんが、その定義は非常に多様で広範です。しかし、気候変動や人権などの社会課題が深刻化する中で、ESG投資やESG経営といった形で、投資や経営の判断にESGの観点を取り入れる動きが加速しています。
グローバルでのESG関連投資金額は、年々増加しており、ESGへの高い関心が示されています。企業がESG経営に積極的に取り組むことは、投資家や顧客からの評価を高め、結果としてブランドイメージや企業価値の向上につながると考えられています。
ESG DDのM&Aにおける必要性
M&Aの目的を持続的成長の実現や競争優位性の向上とするならば、特に環境(E)の観点が注目されています。脱炭素やサーキュラーエコノミーといった環境課題への取り組みは、消費者の価値観や消費マインドの変化を促し、企業のブランドや売上にも影響を与えます。また、環境負荷低減のための設備導入や環境規制対応は将来的なコストにも影響します。
一方で、貧困問題や人権問題といった社会(S)の課題解決を見据えたM&Aも今後増加すると考えられます。現時点では、社会(S)や企業統治(G)の観点は、法令遵守や体制構築といったリスク対応の側面が先行しており、M&Aの文脈では対象企業のデューデリジェンス(DD)や買収後の統合(PMI)において重視されています。
ESG投資の拡大とM&A市場への影響
ESG課題を投資の意思決定に組み込むことを求める「投資責任原則(PRI)」に基づく投資は拡大を続けており、PRIには2024年10月末現在、5,300以上の機関が署名しています。ESG投資の総額は増加を続け、世界の運用資産全体の3分の1程度を占めています。日本でも機関投資家によるESG投資残高は総運用資産残高の多くの割合にのぼると報告されています。
このようなESG重視の動きは、M&A市場にも顕著に現れています。ESG、SDGs、持続可能を目的に組み込んだM&Aは増えており、特に環境(E)においては、脱炭素やカーボンニュートラルをキーワードにしたM&Aが大幅に増加しています。これは、M&Aにおいて対象企業が地球環境や気候変動に適切に対応しているかが、より注目されるようになったことを示しています。
M&Aを通じたESG戦略の具体例
M&Aは、従来の成長戦略を実現する有効な手段であり、ポートフォリオの入れ替えなど大きな変革を行うために用いられてきました。ESGによる社会変革の中で、企業は「環境(E)」をトリガーとした成長戦略を策定しており、その実現と加速化のために、再生エネルギーやグリーン技術への投資、サーキュラーエコノミー実現に向けた投資が増加傾向にあります。
具体的には、以下のようなM&A戦略の類型が見られます。
ポートフォリオの再構築
CO2排出量の多い事業からの撤退を進めつつ、M&Aを活用して売上を拡大する事例があります。大手コングロマリット企業における火力発電事業の売却など、企業の中枢を担ってきた事業のダイベストメント(売却)も多く見られます。
静脈産業への投資
サーキュラーエコノミーの実現を加速するため、日本ではこれまで敬遠されがちだった静脈産業(廃棄物処理、リサイクルなど)へのM&Aを実行し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進する大手商社の事例があります。
マイノリティ出資やアライアンス
現在発展段階にあるものの、多くの企業が取り組んでいるトレンドです。ただし、ポートフォリオのコレクションに終わらせず、シナジーを創出できる事業に投資を行うことが重要です。
これらのM&A戦略を確実に実行し、企業価値の向上につなげるためには、ESGの観点を組み込んだポートフォリオマネジメントが重要です。
▷関連:デューデリジェンスの種類|法務・事業・環境・業界別M&Aも解説
ESG DDの進め方
ESGデューデリジェンス(ESG DD)とは、M&Aにおいて、投資対象のリスクと機会を評価するDDプロセスにESGの観点を組み込んだものです。従来のM&Aにおいても環境DD、法務DD、人事DDなどの一部調査は実施されてきましたが、ESG DDではさらに多岐にわたる項目が挙げられます。
ESG DDの主要な評価項目
ESG DDでは、以下の観点から対象企業を評価します。
環境(E)
- エネルギー消費、CO2排出量
- 資源枯渇(水を含む)、廃棄物、汚染
- 気候変動、温室効果ガスの排出
- 環境対策費用の増加や座礁資産の撤去債務の計上といったコスト面
- 環境に配慮した製品開発による売上増加などの機会
社会(S)
- 労働条件(奴隷労働および児童労働を含む)
- 地域コミュニティ(先住民コミュニティを含む)
- 健康および安全、従業員関係、多様性・包括性
- 人権問題
企業統治(G)
- ESGに関連するKPIに連動した役員報酬制度
- 非財務情報などのESGレポーティング体制
- 役員報酬、贈収賄および腐敗
- 取締役会/理事会の多様性および構成、税務戦略
ESG DDのプロセスと専門性
ESG DDは、従来のビジネス、法務、財務、税務などのDDと併せて実施されるケースが増えています。ESG DDのプロセスは、優先すべきESGに関する課題の特定、対応体制の整備状況、収益化に向けた計画、ESG関連リスクの把握を目指す一連の査定です。
ESG DDには法務DDとは異なる特徴があります。
- 基準の拡大: 各国法令だけでなく、国際人権法などの国際法や、近い将来に制定されうる法令も視野に入れて確認を行います。ISO(国際規格)などのソフトローや、譲受企業側のESGポリシーへの適合性も重要な確認ポイントとなります。
- サプライチェーンのカバー: 対象企業やその子会社だけでなく、人権DDやTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)開示など、サプライチェーン全体をカバーする必要がある項目も少なくありません。
▷関連:人権デューデリジェンスとは?M&Aでの背景・目的・進め方
ESG DDは、時間的な制約があるM&Aプロセスにおいて段階的に評価されます。下表の通り、全体像の把握から結果の定量化まで4つのステップで実施します。
| ステップ | 実施内容 |
|---|---|
| 1. 全体像の把握 | 対象会社のESGに関する全体像を把握することから始めます。全社的なサステナビリティ戦略、ESGの視点から見た事業全体像、経営陣のESGに対する認識、気候変動や人権、コーポレートガバナンスに関する開示情報の質や量などを調査し、対象会社のESGに対する感度を図ります。基本的なESG戦略やESG担当部署がなかったり、開示が不十分であったりすることは、それ自体がリスクと評価される可能性が高いです。 |
| 2. 重要度の高いESG課題の洗い出しと評価 | 対象会社の業種、ビジネス形態、規模、展開地域、ステークホルダーの期待や与える影響などに関する公開資料から、対象企業にとって重要度の高いESG課題や機会を洗い出します。サステナビリティ会計基準審議会(SASB)などのフレームワークも有用です。抽出されたESG課題を中心に、重大なリスクが潜んでいないか、対象企業がそのリスクにどの程度対応しているかを、Q&Aやインタビューを通して深く調査し、評価します。この評価は、ESG課題の重要性(マテリアリティ)と対象企業のリスク対応の成熟度(マチュリティ)という二つの観点から行われます。 |
| 3. 専門的なDDの実施 | 重要性が高く、かつ成熟度が低い(企業の対応が不十分である)と判断された項目については、財務、法務、税務、環境、人事、反贈収賄DDなど、専門的なDDを実施します。TCFD開示やネットゼロ戦略策定など、特定のESG関連業務の拡大や整備をPMI(譲受後の統合プロセス)で目指す場合、これらのESG関連業務についてさらにDDで深掘りする必要もあります。 |
| 4. 結果の定量化とバリュエーションへの反映 | ESG DDの結果は、リスクと機会の検出結果を定量化し、バリュエーションに反映することが不可欠です。環境対策費用の増加や座礁資産の撤去債務の計上、環境に配慮した製品開発による売上増加などの項目が考えられます。ESG DDは、ネガティブチェックやリスク評価にとどまらず、持続的な成長や競争力の確保の源泉となる項目の洗い出しのために実施されます。 |
ESG DDには、TCFD、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)、CSRD(企業サステナビリティ報告指令)など、基準や規制動向の影響を受けるESG領域に関する高い専門性が求められます。競合企業の最新のESG戦略や非財務情報の開示状況、ESG・サステナビリティ部署の設置などの組織運営にも注目が必要です。各領域のESG専門家との協力も不可欠と考えられます。
▷関連:環境DDとは?M&Aでの目的・調査項目・流れ・費用相場と業者選定
M&A後のPMIにおけるESGの対応
M&A実施後における経営統合(PMI)においても、ESGの観点からの対応が重要です。PMIでは、ESGに対するコミットメントの温度差や、取り組みの成熟度が異なる企業を統合することになります。従来のPMIに加えて、ESGの観点を織り込んだ統合基本方針の作成から始め、ESG DDで検出した機会を実現するシナジー施策の検討、ESG関連項目をKPI化し、シナジー施策と合わせて事業計画に反映していく必要があります。
また、環境や社会に配慮し、サプライチェーンにも変革を求める必要が出てきます。組織についても、ESGやサステナビリティ関連部署の統合は全社に影響するものであり、ESG関連の非財務情報の統合を含むガバナンス体制の構築も重要となります。譲受企業の財務情報と同様に、ESGに関連する非財務情報を収集・分析・活用する体制とオペレーションの整備も必要です。
このような多岐にわたる取り組みを通じて、社内外のステークホルダーに対して、ESGに関連する非財務情報を含むM&A戦略、価値創造ストーリーを正しく伝えていかなければなりません。従来のPMIにESGの観点が加わることで、統合に求められる変革の規模は大きくなり、単なる統合にとどまらず、M&Aをきっかけとしたトランスフォーメーションが必要となると言えるでしょう。
PMIにおける具体的な対応事項
PMIにおいては、ESG DDで発見された個別の課題にしっかりと対応することが重要です。関連する取り組みを対象企業において平時化する観点から、ESGに関するガバナンス体制を整備することも重要になります。具体的には、以下の点が考えられます。
- ESG関連ポリシーの整備
- サステナビリティ委員会などのガバナンス体制の整備
- インセンティブ報酬制度とESG関連目標(KPI)の連携
- 定期的なESG DD/人権DDの実施
M&Aの実施によって対象企業が譲受企業のグループ会社となった場合、特に譲受企業が上場会社であるケースでは、コーポレートガバナンス・コードや金融商品取引法/開示府令などで求められているESG情報開示に向けて、関連情報を随時収集しモニタリングできる体制を整備していく必要があります。ESG情報開示については開示基準の策定が近年急速に進められており、今後、開示情報の保証に関する基準が整備されると、そうした情報に関するモニタリングが内部統制の役割としても求められることになります。
▷関連:PMIを成功させるデューデリジェンス|M&A後の統合リスク対策
ESG要素が企業価値向上に与える影響
ESG要素への取り組みは、企業の持続的成長や競争優位性の確保、企業価値評価に大きく寄与します。
リスク低減とブランドイメージ向上
ESGに関連するリスクへの適切な対応は、ビジネスに深刻な影響をもたらす事態を回避し、企業のレジリエンスを高めます。例えば、人権問題や環境規制違反は、企業の信用失墜や訴訟につながる可能性があります。ESG DDを通じてこれらのリスクを早期に特定し、軽減策を準備することで、ネガティブな影響を未然に防ぐことができます。
一方で、ESG経営への積極的な取り組みを示すことは、投資家や顧客からの評価を高め、結果としてブランドイメージや企業価値の向上につながります。脱炭素やサーキュラーエコノミーへの取り組みは、消費者の価値観の変化を促し、企業のブランドや売上にも良い影響を与えます。
資金調達の円滑化
ESG投資の拡大に伴い、投資家は企業のESGに対する取り組みを重視するようになっています。ESG評価が高い企業は、資金調達の面で優位に立つことができます。ESGに配慮したM&Aは、持続可能な事業への投資として評価され、投資家からの資金を得やすくなる可能性があります。
従業員エンゲージメントの向上
環境や社会に配慮した経営は、従業員の企業に対するエンゲージメントを高める要因にもなります。従業員が自社の事業が社会課題の解決に貢献していると感じることは、モチベーションの向上や優秀な人材の獲得・定着につながり、結果的に企業の生産性向上にも寄与します。
ポジティブスクリーニングの視点
ESGの観点をM&Aに組み込む際には、ネガティブチェックやリスク評価にとどまらず、ポジティブスクリーニングの視点も重要です。つまり、対象企業が持つESGに関連する機会を自社に取り込み、新たな価値を創造する視点です。例えば、再生エネルギー技術やグリーン技術を持つ企業を譲受することで、自社の成長戦略を加速させ、収益性だけでなく環境面でのシナジーも創出することが可能になります。このようなM&Aを通じた早期のシナジー創出は、企業にとっても社会全体にとっても良い影響を与えます。
▷関連:人事・労務デューデリジェンスとは?M&Aでの調査項目・費用を解説
国際的なフレームワークと関連法規制
ESG DDを進める上で、国際的なフレームワークや関連法規制との関連性を理解することも重要です。
- TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース): 気候変動関連の財務情報開示を求める枠組みであり、ESG DDやPMIにおいてその要件を満たしているか、あるいは満たすための計画があるかを評価します。
- ISSB(国際サステナビリティ基準審議会): サステナビリティ関連の開示基準を策定しており、その動向に常に注意を払う必要があります。
- CSRD(企業サステナビリティ報告指令): 欧州で適用される企業サステナビリティ報告に関する指令であり、国際的なM&Aにおいては考慮すべき規制です。
- 人権デューデリジェンスの義務化: サプライチェーン全体での人権問題への対応が求められることが多く、多くの国で人権デューデリジェンスの義務化が進んでいます。
- グリーンウォッシュ規制: 実態が伴わない環境配慮の表示(グリーンウォッシュ)に対する規制が各国で強化されており、M&A対象企業が過去にグリーンウォッシュ問題を起こしていないか、将来的なリスクがないかを確認することも重要です。例えば、フランスでは気候レジリエンス法に基づき、誤解を招く広告や包装に罰金や訂正義務を課す制度があります。韓国でも虚偽や誇張した環境配慮を掲げる企業に対し罰金を課す動きがあります。日本でも消費者庁が「生分解性」などの表示に関する措置命令を出しており、これはグリーンウォッシュに関する措置と評価できる動きです。
- 反ESGの動き: 一方で、特に米国ではESG投資に懐疑的な「反ESG」の動きも活発化しており、州の退職金運用におけるESG要素の考慮を禁止したり、特定の産業をボイコットする企業との契約を禁止したりする法案が制定され始めています。日本企業は、これらの相反する規制や投資家の意向のバランスをどのようにとるかを判断する必要があります。
▷関連:海外M&Aのデューデリジェンスの注意点は?言語・法制度・文化の違い
中小企業M&AにおけるESG DD
中小企業を対象とするM&AにおいてESGデューデリジェンスが実施されることは限られています。中小企業M&Aでは財務数値を中心とした企業評価が主流で、ESG観点からの調査は後回しにされがちです。時間やコストの制約から、財務デューデリジェンスや法務デューデリジェンスが優先され、ESGデューデリジェンスは実施されないケースが多いのが実情です。
中小企業におけるリスクと必要性
しかし、ESG経営を重視する動きは、CO2排出「ネットゼロ」を目指す企業の増加に伴い、サプライチェーン全体や金融機関の投融資先を構成する中小企業にとっても避けられない課題となっています。特に製造業や建設業では、環境規制への対応状況、土壌汚染、産業廃棄物の管理など、環境関連のリスクが潜在的に存在します。
譲受企業や金融機関は、ESGの観点を企業評価の重要指標としており、ESGの問題は譲受後の企業価値や事業の持続可能性に大きな影響を与える可能性があります。万が一、環境法令違反が発覚すると、M&A後に多額の是正費用や罰則を負担するリスクがあり、企業価値の低下や社会的評価の悪化にもつながります。
ESG DDの意義
ESGデューデリジェンスを受けることで、会社売却の最終段階での破談による時間的・金銭的損失を防ぎ、汚染対策費用や罰金、ブランド毀損コストを事前に定量化できます。調査結果は表明保証条項や補償条項に反映させることで、M&A後のトラブルを防ぐことが可能です。
中小企業であっても、大手企業のサプライチェーンに組み込まれている場合、ESGリスクの管理が求められる可能性が高く、ESGデューデリジェンスは将来的なリスクの軽減と企業価値の保護を図る有力な手段となります。
▷関連:中小企業M&Aの財務デューデリジェンス|特有の論点と簡易財務DD
業界別のESG DDの着眼点
ESGデューデリジェンスの重点は、対象企業の業界やビジネスモデルによって異なります。DDの対象範囲を合理的に調整する観点から、リスクベースで調査対象項目を限定して行う場合も少なくなく、その場合には対象企業の業種やサプライチェーンの特性、規模などに応じてカスタマイズされたDDが行われます。
具体的な事例
業界毎のESG DDの着眼点の一例を紹介します。
アパレル企業
ESGフレンドリーであることを重要視している場合、原材料の輸入や衣類などの製造を東アジア・東南アジアのサプライチェーンに依存しているならば、そうした地域における製造工程などの調査を通じて、人権を含むESGの観点から改善点の有無を検討することが必要になります。サプライチェーン全体での人権問題への取り組みが重要です。
食品会社
現代奴隷や人権問題のリスクが高いと判断されている地域で事業を展開する食品会社では、人権リスク分析を中心とするDDが実施され、買収後の人権リスクの改善策が提案された事例があります。関連書類のレビューや、対象企業およびサプライヤーへの電話インタビュー、現地視察などが含まれます。
プライベートエクイティ(PE)ファンド
ESGに対する意識の高まりから、対象企業の環境、健康、安全、リスク管理、倫理的な問題、サプライチェーンのESG認証や従業員の福利厚生に関する指標(KPI)を評価し、短期的な価値創造施策と価値向上のための中期的な戦略的イニシアティブを提案する事例もあります。
税理士法人グループによる財務デューデリジェンス
M&Aに潜む財務リスク、見逃していませんか?
よくある質問|ESGデューデリジェンス(FAQ)
ここでは、皆様からよく寄せられるESGデューデリジェンスに関する疑問にお答えします。
ESGデューデリジェンスでは、対象企業の環境、社会、企業統治の各側面を詳しく調査します。具体的には、環境面ではCO2排出量や廃棄物管理、資源利用、社会面では労働条件、人権、多様性、地域コミュニティへの影響、企業統治面では役員報酬、取締役会の構成、贈収賄防止策などを評価します。これにより、潜在的なリスクや機会を特定し、企業価値への影響を分析します。
ESGへの取り組みは企業の価値向上に大きく貢献します。環境規制や社会問題に起因するリスクを低減し、法的な問題や信用失墜を回避できます。また、ブランドイメージや企業評価の向上を通じて、投資家や顧客からの支持を得やすくなり、資金調達も円滑になります。さらに、従業員のエンゲージメント向上にも繋がり、企業の持続的な成長を促進します。
M&Aを通じて持続的成長や競争優位性を目指す企業にとって、ESGデューデリジェンスは不可欠なプロセスとなりつつあります。特に、環境規制が強化されている業界や、サプライチェーンに人権問題などのリスクを抱える可能性がある企業は、本格的なESGデューデリジェンスの実施を検討すべきです。対象企業の業種、規模、展開地域などを踏まえて、リスクと機会を特定し、自社の成長戦略に合致するかどうかを判断することが重要です。
はい、ESGデューデリジェンスでは、対象企業だけでなく、そのサプライチェーン全体におけるESGリスクも対象となる場合があります。特に、人権デューデリジェンスや気候変動関連の課題においては、サプライチェーン全体での取り組みが重要視されています。例えば、アパレル業界では原材料の調達から製造工程まで、人権侵害がないかを詳しく調査することが求められることがあります。
M&AにおけるESG DDのまとめ
ESGデューデリジェンスは、対象企業の環境や社会、企業統治の観点からリスクと機会を評価する重要な手続です。非財務的な側面を詳しく調べることで、企業の持続的成長や競争力を見極め、企業価値の向上につなげることができます。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループとして15年以上の実績を持ち、財務調査に精通した公認会計士が在籍しています。税務を含めた専門的な調査をワンストップで提供します。財務デューデリジェンスをご検討の方は、お気軽にご相談ください。
完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >
著者
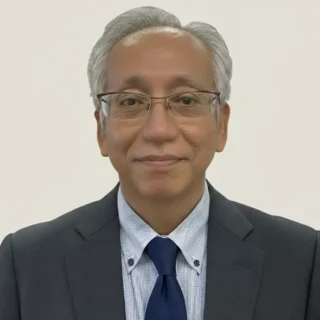
最近書いた記事
 2025年12月31日小売・飲食業M&Aのデューデリジェンス|店舗・FC・ブランド評価
2025年12月31日小売・飲食業M&Aのデューデリジェンス|店舗・FC・ブランド評価 2025年12月31日製造業M&Aのデューデリジェンス|工場・設備・サプライチェーン
2025年12月31日製造業M&Aのデューデリジェンス|工場・設備・サプライチェーン 2025年12月31日IT・ソフトウェア企業のM&Aデューデリジェンス|リスクと評価
2025年12月31日IT・ソフトウェア企業のM&Aデューデリジェンス|リスクと評価 2025年12月31日事業再生M&Aにおけるデューデリジェンスの実務ガイド
2025年12月31日事業再生M&Aにおけるデューデリジェンスの実務ガイド











