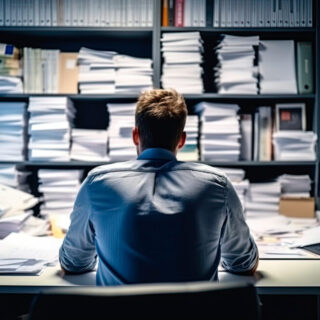自社株買いとは、企業が自社株を購入することです。株主への還元や株価対策などを目的として行われます。本記事では、自社株買いのメリット・デメリット、株価への影響、具体的な手続などを、企業の状況に合わせて分かりやすく解説します。
「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」
そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。
> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ
自社株買いとは
自社株買いとは、企業が過去に発行した自社の株式を、市場や特定の株主から買い戻す行為のことです。会社法でいう「自己株式の取得」の1つで、一般に対価を現金とする有償取引を指します。英語では「Share Buyback」や「Stock Repurchase」と呼ばれます。
企業が自己株式を取得することは、以前は特定の例外を除き原則として禁止されていました。しかし、2001年の商法改正(現在の会社法)により、企業はより柔軟に自社株買いを行えるようになりました。自己株式は、俗に「金庫株」とも呼ばれます。
▷関連:金庫株とは?事業承継で自己株式を活用するメリット・デメリット
自社株買いの目的
企業が自社株買いを行う主な目的は多岐にわたりますが、代表的なものをいくつかご紹介します。
| 自社株買いの目的 | 上場会社 | 非上場会社 |
|---|---|---|
| 株主への利益還元 | 〇(配当と並ぶ主要な還元策、EPS・ROE向上を通じた株主価値向上) | △(株主構成によるが、配当もあり得る) |
| 株価対策 | 〇(市場株価への影響、シグナリング効果) | ×(市場株価がないため、直接的な目的にはならない) |
| 資本効率の改善(ROE向上) | 〇(過剰な自己資本の圧縮) | 〇(資本構成の最適化) |
| 敵対的買収への防衛策 | 〇(市場での株式買い集め阻止) | △(不良株主の防止の目的で極稀にある) |
| ストックオプション・株式報酬 | 〇(インセンティブ制度への活用) | 〇(インセンティブ制度への活用、ただし非公開株のため流動性に課題) |
| 事業承継の円滑化 | ×(通常、関係しない) | 〇(相続対策、後継者への経営権集中) |
▷関連:事業承継とは|3つの承継先・対象・方法や成功事例・進め方も解説
自社株買いのメリット・デメリット
自社株買いは、実施する企業の状況(上場・非上場・中小企業)によって、得られるメリットの側面が異なります。
自社株買いのメリット|非上場会社
非上場企業が自社株買いを行う主なメリットは以下の通りです。
相続税用の資金の確保
中小企業の株式は流動性が低く、市場で容易に売却できないことがほとんどです。そのため、相続時に株式を相続しても、相続税の納税資金に困るケースがあります。自社株買いによって企業が株式を買い取れば、相続人は納税資金を確保できます。
事業承継の円滑化
オーナー経営者から後継者へ事業承継を行う際、相続によって株式が後継者以外の親族などに分散することがあります。自社株買いを活用し、後継者以外の株主から株式を買い戻すことで、後継者に経営権を集中させ、経営の安定化を図ることができます。株主構成をシンプルにすることで、意思決定の迅速化にもつながります。
▷関連:株式譲渡による事業承継|相続・贈与・売買の方法、税金の特例も解説
自社株買いのメリット|社員
自社株買いは主に株主向けの施策ですが、従業員にとっても間接的なメリットや、関連する制度を通じて直接的なメリット・デメリットが生じる可能性があります。
勤労意欲を高める
自社株買いによって取得された株式が、ストックオプションや従業員向けの株式報酬制度に活用される場合があります。従業員が自社の株式を持つことで、会社の業績や株価向上に対する関心が高まり、「会社の成長が自身の利益につながる」という意識が生まれます。これは、仕事へのモチベーション向上や、会社への貢献意欲を高める効果が期待できます。また、魅力的なインセンティブ制度は、優秀な人材の獲得や定着にもつながる可能性があります。
資産形成がしやすくなる
従業員持株会制度がある会社では、従業員は給与天引きなどを利用して、毎月少額から自社株を積み立て購入することができます。これは、長期的な資産形成の一つの手段となり得ます。通常、従業員持株会を通じて株式を購入する場合、奨励金が支給されるなど、有利な条件で購入できるケースもあります。株式投資の経験がない従業員にとっても、比較的始めやすい資産形成方法と言えるでしょう。
資産が一極集中するリスクも
一方で、従業員が自社株を多く保有することにはリスクも伴います。従業員にとって、給与(労働収入)を得ている会社と、資産(株式)を保有している会社が同じであるということは、リスクが集中している状態と言えます。万が一、会社の経営状況が悪化した場合、給与が減ったり、最悪の場合は職を失ったりするリスクに加えて、保有している自社株の価値も大きく下落し、資産まで失ってしまう可能性があります。資産運用においては、リスク分散が基本原則であり、自社株への過度な集中投資は避けるべきという考え方もあります。
自社株買いのメリット|上場会社
上場企業が自社株買いを行う主なメリットは以下の通りです。
株主への利益還元
企業が得た利益を株主へ還元する方法としては、配当金の支払いが一般的です。自社株買いも、配当金と同様に株主への利益還元策の一つとして位置づけられています。自社株買いを行うと、市場に流通する株式数が減少します。その結果、1株当たりの利益(EPS: Earnings Per Share)や株主資本利益率(ROE: Return On Equity)といった指標が改善する傾向があります。これは、株主が保有する株式の価値向上につながるため、間接的な利益還元と見なされます。
株価対策
自社株買いは、株価を意識した対策としても用いられます。市場に流通する株式数が減ることで、株式の需給バランスが変化し、株価が上昇する可能性があります。特に、株価が企業の実質的な価値よりも低いと判断される場合に、株価を適正な水準に近づける目的で実施されることがあります。また、自社株買いの発表自体が、市場に対して「企業が自社の株価を割安だと考えている」というポジティブなシグナルを送る効果(シグナリング効果)も期待されます。
資本効率の改善(資本の最適化)
企業は、事業活動に必要な資金を負債(借入金など)と自己資本(株主からの出資金や利益剰余金など)で賄っています。この負債と自己資本のバランス(資本構成)を、企業価値を最大化する観点から最適な状態に保つことが重要です。自己資本が過剰になっている場合、自社株買いによって自己資本を減らし、負債とのバランスを調整することで、資本効率を高めることができます。
具体的には、株主資本利益率(ROE)の向上が期待できます。ROEは「当期純利益 ÷ 自己資本 × 100%」で計算され、企業が自己資本をどれだけ効率的に使って利益を生み出しているかを示す指標です。自社株買いにより自己資本が減少すれば、同じ利益額でもROEは上昇します。一般的にROEが高いほど、効率的な経営が行われていると評価されます。ROEの向上は、投資家からの評価を高め、株価を下支えする効果が期待できます。
敵対的買収への防衛策
敵対的買収とは、対象企業の経営陣の同意を得ずに、一方的に株式を買い集めて経営権を取得しようとする行為です。自社株買いは、この敵対的買収に対する防衛策としても機能します。自社株買いによって市場に流通する株式数を減らすことで、買収者が買収に必要な株式数を確保しにくくなります。また、株価が上昇すれば、買収コストが増加するため、買収を断念させる効果も期待できます。さらに、安定株主(経営陣に友好的な株主)に自社株を保有してもらうことで、経営の安定化を図ることも可能です。
ストックオプションや株式報酬制度への活用
自社株買いで取得した株式(金庫株)は、役員や従業員に対するインセンティブプランであるストックオプション(新株予約権)の行使や、株式報酬制度(譲渡制限付株式など)のために利用されることがあります。企業が成長し株価が上昇すれば、ストックオプションや株式報酬を受け取った役員・従業員の利益も増加するため、業績向上への貢献意欲を高める効果が期待できます。
自社株買いのデメリット(税金など)
多くのメリットがある一方で、自社株買いにはデメリットや注意すべき点も存在します。
財務状況が悪化する可能性(自己資本比率の低下)
自社株買いを行うには当然ながら資金が必要です。企業の内部留保(利益剰余金)などを使って株式を買い戻すため、手元資金が減少し、自己資本も減少します。 自己資本比率は「自己資本 ÷ 総資産 × 100%」で計算され、企業の財務健全性を示す重要な指標です。自己資本比率が低下すると、借入への依存度が高まっていると見なされ、金融機関からの信用格付けが悪影響を受けたり、借入条件が厳しくなったりする可能性があります。過度な自社株買いは、企業の財務基盤を脆弱にするリスクがあるため注意が必要です。
株価効果の不確実性
自社株買いが必ずしも株価上昇につながるとは限りません。株価は、企業の業績だけでなく、市場全体の動向、経済情勢、投資家心理など、様々な要因によって変動します。自社株買いを発表しても、市場環境が悪ければ株価が下落することもありますし、効果が一時的で長期的な上昇にはつながらないケースもあります。株価対策としての効果は不確実であることを認識しておく必要があります。
一過性の利益還元になる恐れ
配当金は、安定した利益が出ている限り継続的に支払われることが期待される株主還元策です。一方、自社株買いは、企業の財務状況や経営判断によって、特定の時期に一時的に行われることが多い施策です。そのため、株主にとっては、配当金のような継続的な還元とは異なり、一過性のものと受け取られる可能性があります。長期的な視点を持つ投資家にとっては、必ずしも満足度の高い還元策とは言えないかもしれません。
市場の歪みを招く可能性
自社株買いは、市場での株式供給量を人為的に減らすことで株価を押し上げる効果を狙うものです。しかし、これが企業の फंडामेंटल(基礎的)な価値向上に基づかない株価操作であると見なされる場合、市場の公正性を歪めるという批判もあります。特に、経営陣が自身の株式報酬(ストックオプションなど)の価値を高めるために自社株買いを利用していると見られる場合には、株主との利益相反が指摘される可能性もあります。
財源規制
企業が自由に自社株買いを行えるわけではありません。会社法では、株主への過度な利益還元を防ぎ、会社の債権者を保護する観点から、自社株買いに使用できる財源に制限(分配可能額規制)を設けています。 具体的には、自社株買いに充てられる金額は、その時点での「分配可能額」の範囲内に限られます。分配可能額は、大まかに言うと、会社の純資産額から資本金、資本準備金、利益準備金などを差し引いた額(主にその他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額)です。この分配可能額を超えて自社株買いを行うことはできません。
株主への「みなし配当」課税
株主が保有する株式を、発行会社である企業に売却(自社株買いに応じる)した場合、税務上、その譲渡対価の一部が「配当」とみなされることがあります。これを「みなし配当」と呼びます※。 個人の株主の場合、みなし配当部分は配当所得として総合課税(累進課税)または申告分離課税(一定の要件を満たす上場株式等の場合)の対象となり、所得税・復興特別所得税・住民税が課税されます。
※ みなし配当とされる金額は、株主が株式を売却して得た金額のうち、その株式に対応する会社の「資本金等の額」を超える部分です。一方、資本金等の額以下の部分は株式の譲渡所得(または譲渡損失)として扱われ、申告分離課税の対象となります。 みなし配当の計算や課税関係は複雑なため、専門家への相談が推奨されます。
▷関連:事業承継の相談先を比較|中小企業のための選び方・おすすめ先を紹介
自社株買いの価格
自社株買いする際の株価について、非上場会社と上場会社に分けて説明します。
非上場株式の自社株買いの価格
非上場会社は市場価格が存在しないため、株価の算定方法が重要となります。一般的に用いられる方法は、類似業種比準価額方式(類似する上場企業の株価を参考に算定)と純資産価額方式(会社解散時に得られる資産総額を発行済株式数で除して算定)です。実務では、複数の方法を組み合わせ、それぞれの算定価格を比較した上で、より高い方を採用することが多いです。また、企業の将来性や成長性、配当実績なども考慮し、株主との交渉を通じて最終的な価格を決定します。
▷関連:非上場株式の評価方法|事業承継における税務とM&Aの時価
上場株式の自社株買いの価格
上場会社の自社株買いは、証券取引所における市場価格を基準として実施されます。主な取得方法は、市場取引と公開買付け(TOB)です。市場取引では、東京証券取引所などで形成される市場価格で株式を買い付けますが、株価への影響を避けるため、買付時間帯、価格、数量に一定の制限(30分ルールや価格制限等)が設けられています。TOBでは、特定の大株主から買い取る場合、市場価格よりもディスカウントした価格とすることがあります。いずれの方法でも、市場の需給関係により客観的に形成された市場価格が基本的な価格決定の基準となります。
自社株買いと株価への影響
自社株買いが株価に与える影響は、一般的にポジティブとされていますが、そのメカニズムと注意点を理解しておくことが重要です。
- 株価上昇のメカニズム:自社株買いは、ときに以下のような因果関係で市場株価を高めることがあります。
- 需給改善:自社株買いにより、市場に流通する株式数が減少します。需要が変わらなければ、供給が減ることで株価は上昇しやすくなります。
- 1株当たり利益(EPS)の向上:発行済株式数が減るため、同じ利益額でも1株当たりの利益は増加します。EPSは株価を評価する重要な指標の一つであり、その向上が株価上昇につながることが期待されます。
- 自己資本利益率(ROE)の向上:自己資本が減少するため、ROEが改善します。ROEの向上は、資本効率が良いと評価され、投資家の買い意欲を刺激する可能性があります。
- シグナリング効果:企業が自社株買いを行うこと自体が、「自社の株価は割安である」「将来の成長に自信がある」というポジティブなメッセージを市場に送る効果があります。
株価への影響に関する注意点
前述の通り、自社株買いが常に株価上昇を保証するものではありません。市場全体の地合いが悪ければ、自社株買いの効果は限定的になる可能性があります。また、自社株買いの規模やタイミング、企業の財務状況なども株価への影響度を左右します。
自社株買いの計算方法
自社株買いに関連する重要な指標の計算方法を解説します。
1株当たり利益(EPS)
EPS = 当期純利益 / (発行済株式総数 – 自己株式数)
自社株買いを行うと、分母の「発行済株式総数 – 自己株式数」が減少するため、EPSは上昇します。
株価収益率(PER)
PER = 株価 / EPS
PERは、株価が1株当たり利益の何倍かを示す指標で、株価の割安・割高を判断する際に用いられます。自社株買いによってEPSが上昇すると、株価が変わらなければPERは低下し、株価が割安であると評価される可能性があります。
自己資本利益率(ROE)
ROE = (当期純利益 / 自己資本) × 100 (%)
自社株買いは、自己資本(純資産)を減少させるため、ROEを向上させる効果があります。
自己株式取得価額の上限
会社法で定められた分配可能額が、自社株買いに使える金額の上限となります。分配可能額の計算は複雑ですが、簡略化すると以下のようになります。
分配可能額 = (その他資本剰余金 + その他利益剰余金) – (自己株式の帳簿価額 + その他)
正確な計算には、のれん等調整額や評価・換算差額なども考慮する必要があるため、会計専門家への確認が必要です。
▷関連:事業承継コンサルティングとは?必要資格・支援機関一覧・報酬など
自社株買いのルール
最後に、自社株買いに関する主なルールについて説明します。
自社株買いの手続
自社株買いの具体的な手続は、会社法で定められています。
株主総会または取締役会での決議が必要
自社株買いを行うには、原則として株主総会の普通決議が必要です。ただし、取締役会設置会社においては、定款に定めることで、特定の株主からの取得を除き、取締役会の決議によって自社株買いを行うことが認められています(会社法第165条2項)。 決議では、取得する株式の種類と総数、株式を取得する代わりに交付する金銭等の内容とその総額、株式を取得できる期間(1年以内)などを定める必要があります(会社法第156条1項)。
具体的な取得方法
自社株買いを実行する方法には、いくつかの選択肢があります。企業の状況や目的に応じて適切な方法を選択することが重要です。以下の表は、自社株買いの主な方法とその特徴をまとめたものです。
| 取得方法 | 内容・仕組み | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 市場買付け | 上場企業が自社株買いを行う最も一般的な方法です。証券取引所が開設している市場を通じて、不特定の株主から自社の株式を買い付けます。市場の取引時間内(ザラ場)に買い注文を出す方法や、立会時間外取引(ToSTNeT市場など)を利用する方法があります。 | 市場での買付けは、株価への影響を抑えながら、機動的に株式を取得できるメリットがあります。 |
| 公開買付け(TOB:Take-Over Bid) | 市場外で、あらかじめ買付け価格、期間、株数などを公告し、不特定の株主から株式を買い付ける方法です。 | – 市場での買付けよりも短期間で大量の株式を取得したい場合や、株価を一定の価格に固定して買い付けたい場合に利用されます – 自社株買いだけでなく、他の企業の株式を取得(譲受)する際にも用いられる手法です |
| 特定の株主からの相対取引 | 市場を通さずに、特定の株主(例えば、創業家や大株主など)と個別に交渉し、合意した価格と数量で株式を買い取る方法です。 | – 非上場企業(中小企業)の事業承継、相続対策などでよく利用されます – 特定の株主から市場価格よりも著しく有利な価格で取得する場合などは、他の株主の利益を害する可能性があるため、株主総会の特別決議が必要になるなど、手続が加重される場合があります(会社法第160条) – 特定の株主から取得する場合、他の株主にも「自分たちの株式も買い取ってほしい」と請求する権利(売主追加請求権)が認められるケースがあり、注意が必要です(会社法第160条2項、3項) |
| その他(第三者割当増資など) | 直接的な自社株買いとは異なりますが、結果的に自社株買いと同様の効果をもたらす方法として、特定の第三者(取引先や金融機関など)に新株を発行(第三者割当増資)して資金を調達し、その資金で市場から自社株を買い戻すといったスキームも考えられます。 | 手元資金が不足している場合に、資金調達と自社株買いを同時に行うようなケースで利用されることがあります。 |
自社株買い後の自己株式の扱い
自社株買いで取得した金庫株は、発行済株式数には含まれますが、議決権や配当を受ける権利、剰余金分配請求権などは有しません。 取得した自己株式は、以下のいずれかの方法で処理されます。
自社株の保有
将来のストックオプションや株式報酬、M&A(合併や株式交換など)の対価として利用するために、会社がそのまま保有し続ける。
自社株の消却
株式を消滅させる手続です。自己株式を消却すると発行済株式数が減少し、資本効率の改善や株主還元の効果がより明確になります。消却には取締役会決議(取締役会非設置会社では株主総会決議)が必要です。
自社株の処分(売却)
保有している自己株式の譲渡は、市場で売却したり、特定の第三者に譲渡したりします。資金調達の手段として用いられることがあります。
自社株買いの会計処理
自社株買いを行った際の会計処理は、取得時、保有時、処分時(売却時)、消却時で異なります。
取得時
取得した自己株式は、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除する形で表示されます(自己株式としてマイナス計上)。
保有時
保有している自己株式には、配当金は支払われません。期末の評価替え(時価評価)は行いません。
処分時(売却時)
自己株式を売却した場合、売却価額と帳簿価額(取得原価)との差額は、「自己株式処分差益」(純資産の部のその他資本剰余金)または「自己株式処分差損」(純資産の部のその他資本剰余金から控除)として処理します。損益計算書には計上されません。
消却時
自己株式を消却した場合、消却する自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額します。その他資本剰余金が不足する場合は、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額します。
会計処理は専門的な知識を要するため、公認会計士に相談することをお勧めします。
▷関連:事業承継アドバイザリーとは?役割・依頼メリット・選び方・資格
自社株買いのまとめ
自社株買いは、株主還元やROE向上、株価対策などの目的で活用されます。特に非上場の中小企業では、後継者以外の株主から株式を買い取ることで経営権を集中させ、相続税の納税資金を確保できるため、事業承継対策として有効です。一方で、財務状況悪化リスクや財源規制、みなし配当課税などの注意点もあります。
みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業M&Aに特化した豊富な実績を持つアドバイザーが多数在籍しています。自社株買いを含む事業承継の税務・法務サポートもワンストップで対応可能です。ぜひご相談ください。
完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >
著者

- 事業法人第二部長/M&A担当ディレクター
-
ヘルスケア分野に関わる経営支援会社を経て、みつきコンサルティングでは事業計画の策定、モニタリング支援事業に従事。運営するファンドでは、投資先の経営戦略の策定、組織改革等をハンズオンにて担当。東南アジアなど海外での業務経験から、クロスボーダー案件に関しても知見を有する。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上
監修:みつき税理士法人
最近書いた記事
 2026年1月4日M&Aの価格ギャップとは?売り手・買い手の評価の乖離の原因と対策
2026年1月4日M&Aの価格ギャップとは?売り手・買い手の評価の乖離の原因と対策 2026年1月4日会社売却の希望価格はどう決める?計算方法・高く売る秘訣を解説
2026年1月4日会社売却の希望価格はどう決める?計算方法・高く売る秘訣を解説 2026年1月4日会社売却の手取り額はいくら?オーナーの税金計算・最大化する方法
2026年1月4日会社売却の手取り額はいくら?オーナーの税金計算・最大化する方法 2026年1月3日会社売却で家族の反対に遭ったら?円満な承継を実現する説得方法
2026年1月3日会社売却で家族の反対に遭ったら?円満な承継を実現する説得方法